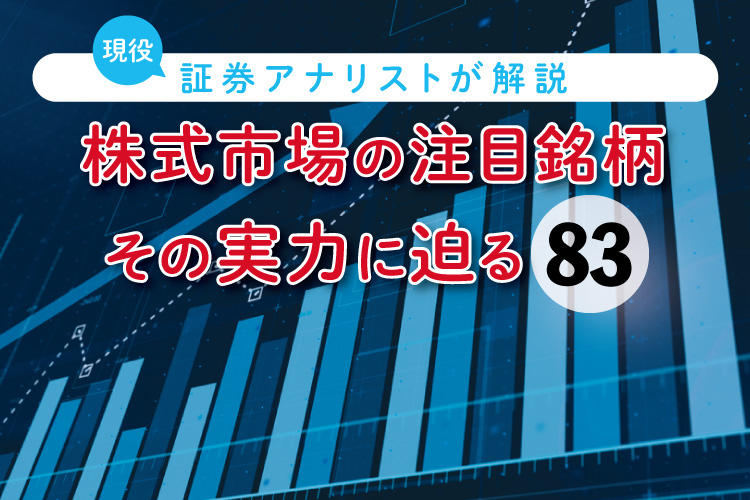700人以上所属する日本放送作家協会(放作協)がお送りする豪華リレーエッセイ。テレビ、ラジオ、動画配信も含めて様々なコンテンツの台本や脚本を執筆する放送作家&脚本家、そして彼らと関わる様々な業界人たち・・・と書き手のバトンは次々に連なっていきます。ヒット番組やバズるコンテツを産み出すのは、売れっ子から業界の裏を知り尽くす重鎮、そして目覚ましい活躍をみせる若手まで顔ぶれも多彩。この受難の時代に力強く生き抜くユニークかつリアルな処世術はきっと皆様の参考になるはず!
連載第212回は、FMシアターなどラジオドラマでもおなじみ、シナリオライターの門前日和さん。
貧乏エピソードに事欠かず
 門前日和
門前日和シナリオライター
小学生の頃から社会人になるまで、ずっとあだ名が「貧乏」でした。
すごいと思いませんか?
環境が変わり、付き合う人たちも変わっていくのに、それでもずっと「貧乏」と呼ばれ続けるなんて。
もちろん、実際にお金がなかったことが最大の要因ですが、それだけでなく、常に貧乏な雰囲気を醸し出していたのだと思います。
小銭を拾う旅に出たり、落ちているものを拾って食べたり、太ももがすべて見えるぐらいの破れたジーパンを履いていたり、パチスロや演劇にハマっていたので仕方ないのですが……。
 お金がないだけでなく、常に貧乏な雰囲気を醸し出していた
お金がないだけでなく、常に貧乏な雰囲気を醸し出していたというわけで、「貧乏」はわたしにとって、ずっと身近な存在でした。
そして、貧乏だったからこそ出会った世界があり、今回はそのいくつかをご紹介させてください。
忘れられない内職
わたしが中学生のとき、父が椎間板ヘルニアを患い、働けない時期がありました。
それで母がいくつかの内職を始め、わたしも手伝ったのですが、そのなかに忘れられない内職がありまして……。
それは、紙を折って花を作る仕事です。
折り紙よりも薄いティッシュのような紙を折って花を作るのですが、その当時、なんと1個10銭という値付けでした。
円じゃなくて銭ですよ。1時間かけて100個作っても、もらえるお金は10円。
ダンボールにたまった紙の花を前にして、絶望したのをよく覚えています。
それでも母はやり続け、1万円ぐらい稼いでいました。
10万個作ったということですから、とんでもないですよね。
そのころから我が母のことを、世が世なら幕府を作ったぐらいの豪傑なんじゃないかと思うようになりました。
※ちなみにネットで検索すると、今は1個あたり5円から20円が相場のようです。
いい時代になりました。ただ募集はほとんどないみたいですが……。
父のアルバイト
それからしばらくして、ヘルニアが治った父が、遠くに出稼ぎへ行ったり、アルバイトをしたりするようになりました。
よく覚えているのは、バキュームカーの清掃のバイト。
バキュームカーとは、汲み取り式のトイレから大便を回収する車のことです。
つまり大便を洗い流してキレイにする仕事を父はやることになりました。
そしてバイト初日。
張り切って出かけた父は泣きそうな表情で帰ってきました。
「匂いが取れねえよ……」
どんなにシャワーを浴びても、臭いような気がするんだそうです。
その日の夜、父はずっとうなされていました。
わたしはそっと寝室を抜け出して、父の部屋をのぞきました。
すると父は「ああああああああああ」と叫んで、ガバっと起き、自分の体の匂いを必死に嗅いでいました。
あとで聞いたらうんちの川で溺れる夢を見ていたそうです。
なんてつらい夢なんでしょう……。
結局、父はすぐにそのアルバイトをやめることになりました。
 バキュームカー清掃の仕事をした父は、うんちの川で溺れる夢を見てうなされていた。
バキュームカー清掃の仕事をした父は、うんちの川で溺れる夢を見てうなされていた。下水道の普及によりバキュームカーの数は減っていると思いますが、今でも必要とされている地域は少なくないでしょう。
そして、バキュームカーはその地域の衛生を支えているのだと思います。
バキュームカーの清掃をされている方々を心から尊敬しています。
※かなり昔の話なので、今は、もっと楽に洗浄する方法があるのかもしれません。
また、父はこのことをまったく覚えていませんでした……。
電気を止められた
そんなこんなの我が家だったので、お金を稼ぐことの大変さを肌に刻み込まれて育ちました。そしてこのような状況にもかかわらず、大学に進学させてもらい、とても感謝しています。今ならその大変さがきちんと想像できます。
でも当時のわたしはよくわかっていませんでした……。
わたしは大学に進学後、演劇とパチスロにハマり、光熱費すら払えない生活を送ることになります。
電気を止められたときには「テレビの光で暮らせばいいか」とのんきに考えていました。
しかし、テレビの電源を入れても映りません。
当たり前ですよね。電気がなければテレビがつくはずありません。
自分の愚かさに愕然としました。
それから電気代を払うまでは、太陽が昇ったら起きて、太陽が沈んだら寝る生活をしていました。
東京でも意外と星の光って明るいんですよね。
うまく眠れない夜には、カーテンを全開にし、星明かりや車のヘッドライトによってまだら模様になった部屋の中で、小説を読みました。そうやっていると、まるで別世界にやってきたような、宇宙空間に浮かんでいるような、不思議な感覚になったのをよく覚えています。
 電気を止められ月や星の光で照らされた部屋は、まるで別世界のようだった
電気を止められ月や星の光で照らされた部屋は、まるで別世界のようだったお金がなくなると、世の中が色彩のない灰色の世界に見えます。
でも、そのなかで必死にもがいたことは、とても貴重な体験だったように思います。
ちなみに、これら以外にも1カ月間米と塩だけで食事をしていたら体がおかしくなった話や、落ちている空き缶を集めてお金にしようとした話など、貧乏にまつわるエピソードはまだまだたくさんあります。
それは、またどこか別の機会で。
次回は島敏光さんへ、バトンタッチ!
放送作家の地位向上を目指し、昭和34年(1959)に創立された文化団体。初代会長は久保田万太郎、初代理事長は内村直也。毎年NHKと共催で新人コンクール「創作テレビドラマ大賞」「創作ラジオドラマ大賞」で未来を担う若手を発掘。作家養成スクール「市川森一・藤本義一記念 東京作家大学」、宮崎県美郷町主催の「西の正倉院 みさと文学賞」、国際会議「アジアドラマカンファレンス」、脚本の保存「日本脚本アーカイブズ」などさまざまな事業の運営を担う。