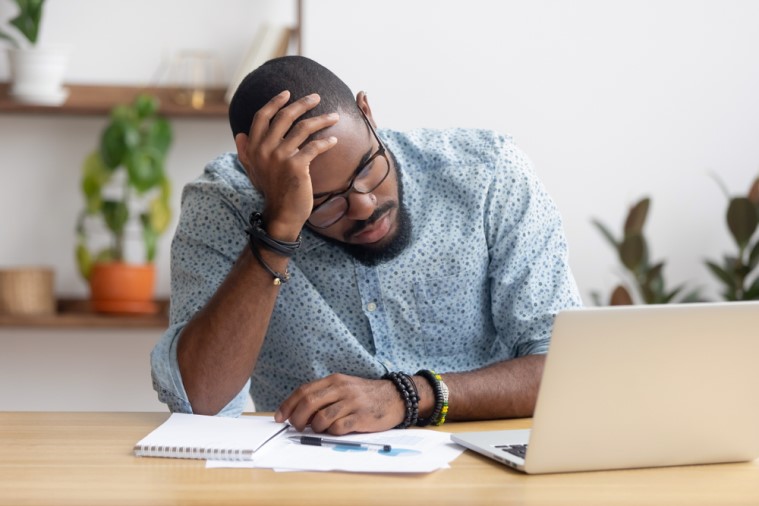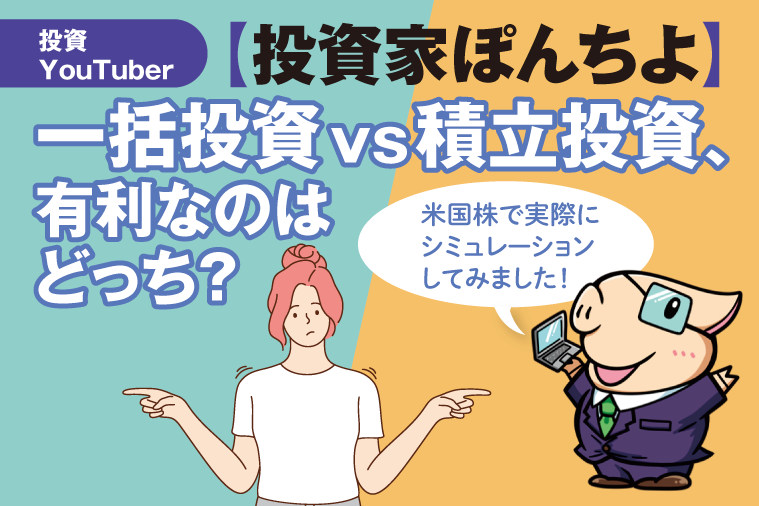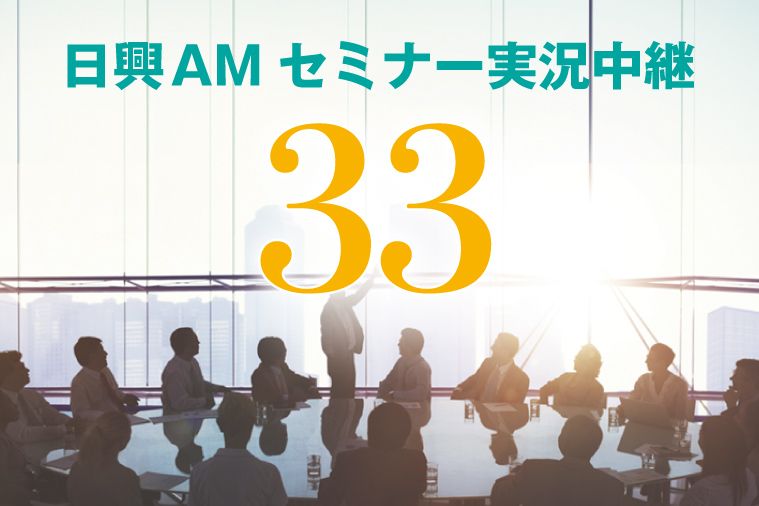2019年6月の金融審議会・市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(以下:報告書)で、公的年金だけでは老後資金が不足してしまうという試算が発表されました。その不足額が2000万円でしたので、「老後2000万円問題」として世間で大きくクローズアップされました。そのため、2000万円を1つの目安として老後に向けた資産形成を行っている方も多いかと思われます。
この記事では、老後資金が2000万円不足する前提条件などを確認しながら「老後2000万円問題」について見ていきます。
- 老後資金が2000万円不足する試算のモデルは「高齢夫婦無職世帯」
- 65歳以降も仕事で収入を得られれば、老後資金の不足額を引き下げられる
- 金融資産を取り崩す時期を後ずれさせれば、その間を資産運用に充てられる
老後資金が2000万円不足する前提は
報告書では、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみ)を対象に、月の実収入から実支出を引いた不足額をベースに老後資金の不足額を算出しています。
月の実収入と実支出の内訳は以下の通りです。
出所:第21回市場ワーキング・グループ 厚生労働省資料 p.24
これに30年間(360カ月)を掛けると約2000万円、20年間(240か月)では約1300万円と試算しています。
ただし、高齢夫婦無職世帯が不足額を算出する前提になっている点に注意が必要です。
前期高齢者(65歳~74歳)の実際の就業率は?
総務省「労働力調査(基本集計)2024年平均結果」によると、60~64歳と前期高齢者(65~74歳)までの就業率は下表のようになります。
| 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 84.0% | 62.8% | 43.8% |
| 女性 | 65.0% | 44.7% | 27.3% |
出所:労働力調査(基本集計)2024年平均結果 p.6を参考に筆者作成
男性では60~64歳の就業率は84.0%、65~69歳が62.8%、70~74歳でも43.8%と、10人に4人以上が仕事による収入を得ていることがわかります。
また、女性は60~64歳で65.0%、65~69歳が44.7%、70~74歳で27.3%と男性に比べて就業率は低くなりますが、70~74歳でも約4人に1人以上が仕事による収入を得ています。
必要な老後資金を2000万円からいくら引き下げられる?
仕事による収入で月々の不足額をカバーできた場合、目標額を2000万円から引き下げることも考えられます。
以下では、69歳まで働いたケースと74歳まで働いたケースの2つで目標額を試算してみました。
69歳まで仕事をした場合
不足分の月5.4万円を、69歳まで仕事による収入でカバーすることができたとすると、老後2000万円問題の前提である30年間ではなく、25年間と5年間短縮することができます。
その場合の不足額合計は約1600万円(5.4万円×300カ月)となり、約400万円少なくなります。
74歳まで仕事をした場合
同様に、不足分の月5.4万円を74歳まで仕事による収入でカバーすることができたとすると、30年間ではなく20年間と10年間短縮することができます。
その場合の不足額合計は約1300万円(5.4万円×240カ月)となり、約700万円少なくなります。
金融資産を取り崩す時期を後ずれさせるメリットは?
仕事の収入で月々の老後資金の不足分をカバーできると、金融資産を取り崩す時期を後ずれさせ、その間を資産運用の期間にあてることが可能になります。
たとえば、65歳時点で1000万円の金融資産を保有していたとして、それを元本に5年間・10年間、年利回り3%・5%で運用した場合、取り崩しを開始する時の金融資産を示したのが下図です。
| 運用利回り (複利) |
69歳まで 5年間運用 |
74歳まで 10年間運用 |
|---|---|---|
| 3% | 1159万円 | 1344万円 |
| 5% | 1340万円 | 1628万円 |
金融資産1000万円の場合は、75歳から取り崩しを開始できれば、年利回り3%の運用で老後の不足額をカバーできることがわかります。
70歳からの取り崩しでは、年利回り3%では毎月の取り崩し額が3.86万円(1159万円÷300カ月)、5%では4.46万円となり、不足額5.4万円を下回ります。そのため、支出の見直しが必要になってきます。
次に、65歳時点で1200万円の金融資産を保有していたケースが下図です。
| 運用利回り (複利) |
69歳まで 5年間運用 |
74歳まで 10年間運用 |
|---|---|---|
| 3% | 1390万円 | 1612万円 |
| 5% | 1608万円 | 1953万円 |
このケースでは、70歳から取り崩す場合は5%以上の運用利回りが必要になり、75歳から取り崩す場合は、3%あれば不足額(1300万円)を超える金融資産を形成することが可能となります。
このように、65歳以降も就労を継続し、さらに65歳までに形成した金融資産を運用することで、老後に用意する資金を減らすことを考えられるようになります。
仕事の収入を見込む場合の注意点
仕事の収入を見込む場合の注意点は、就労が可能な心身の健康をいつまで保てるかどうかにより、見込める収入が変動してしまうリスクがある点です。
仕事の収入を見込む場合は、ご自身の健康状態を考えながらいくつかシミュレーションを行い、無理のない範囲で取り崩し時期を後ずれさせることを検討しましょう。
まとめ
以上、老後2000万円問題の前提条件を確認し、実際の就業率から毎月の不足分を金融資産で賄う時期を後ずれさせた場合についての不足額について試算を行いました(インフレを考慮していません)。
実際、毎月の不足額は世帯により異なります。2000万円以外の金額で試算する必要はありますが、計算方法などは変わりません。夏の休暇を利用して、ご自身にあった金額(不足額)や年利回りを設定して必要な老後資金を試算してみはいかがでしょうか。