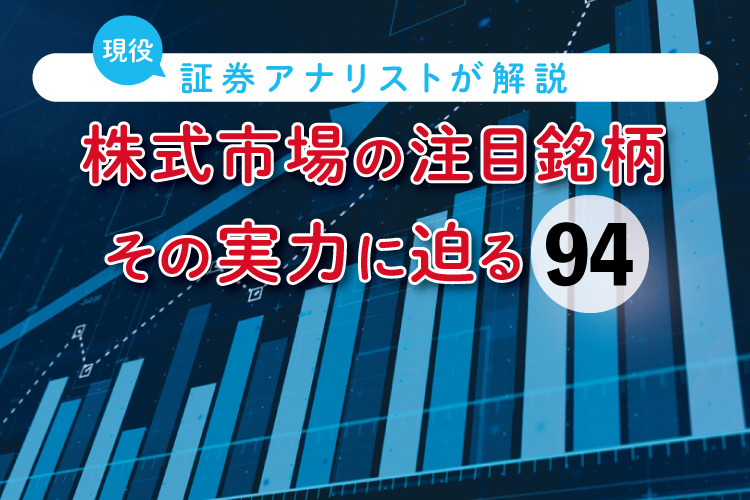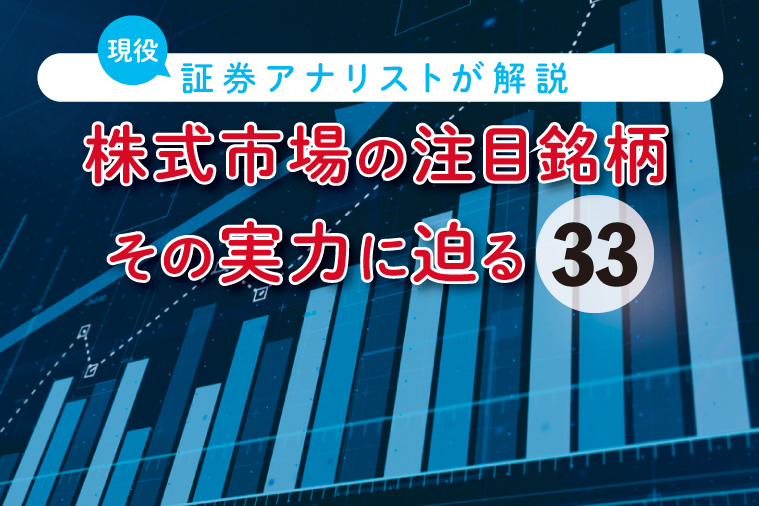「預金なら安心」って本当なの? 「元本保証」って、実際に何を保障してくれるの? 実は、現金にもリスクが潜んでいるのです。本連載ではそんな「現金のリスク」を切り口に、お金のほんとうの価値を守るための資産運用について考えていきます。今回は、高まりつつある金融市場の不確実性に備えて、配当や分配金に着目した投資の可能性を検討します。
- 不確実性が高い時代でも投資が必要なのは、インフレによるお金の目減りを防ぐため
- 利益が非課税となるNISAを活かすには、売却益より配当金を狙うことを考えたい
- 高配当企業や増配企業に加えて、利回りが魅力的なJ-REITも選択肢に挙がる
なぜ投資をするのかを振り返りつつ、選択肢を考える
ロシアのウクライナ侵略問題とアメリカの関税問題に加えて、イスラエルとイランとの間で戦争が勃発し、原油も急騰しました。海外では不確実性が高まっています。
もちろん国内にも影響があります。その国内に目を向けると、「令和の米騒動」は落ち着きそうですが、物価は確実に上がっています。
このような時代でも、なぜ投資が必要なのかを振り返ります。そして、その選択肢についても考えます。
なぜ投資が必要か……物価の上昇と同水準の利回りをめざして
そもそも、なぜ投資が必要なのでしょうか?
その理由として、「収入を増やす」手段として投資を挙げる人が多いと思います。いわゆる「お金に働いてもらう」という考え方です。もちろん、そうした考え方もありです。「自身も働く」・「お金も働く」とは、家計の収入源を増やすということですからね。
では、「ウチの家計は給料だけで十分だから、投資は不要」ということなのでしょうか?
「預金の目減り」という言葉があります。これは「預金の利率<物価の上昇率(=消費者物価指数)」という意味です。
預金の利率は「1年当たり」で表示されることが多いですし、消費者物価指数も「対前年比=1年前」で表示されます。つまり「物価の上昇」に「預金の利率」が追い付いていない、という意味です。
| 時期(2025年) | 上昇率・利率 | |
|---|---|---|
| 消費者物価指数(※) | 5月 | 3.5% |
| メガバンク定期預金 1年利率 |
6月22日確認 | 0.28% |
| ネット銀行定期預金 1年キャンペーン利率 |
6月22日確認 | 0.80% |
| 信用組合非組合員 定期預金1年利率 |
6月22日確認 | 1.25% |
※前年同月比。総合指数は、2020年を100として111.8
それこそ、1年や2年でしたら「大したことはない」と思われるかもしれません。では、これが3年も5年も続くとしたら、いかがでしょうか?
日本銀行がマイナス金利の解除を宣言し、「金利ある世界」になったのは2024年3月のことでした。これにより、定期預金や国債の利率の魅力が増したのは言うまでもありません。
しかし日本銀行は「インフレ率(=物価の上昇率)目標2%」を取り下げたわけではありません。「預金の目減り」を防ぐためにも投資は必要なのです。
NISAを活かして「預金の目減り」を防ぐには?
NISAは株式や投資信託の売却益や配当金(普通分配金を含む)に対する課税をゼロにするというものです。逆に言えば、NISAでは売却益や配当金を得られないと無意味ということにもなります。
冒頭に申し上げたとおり、不確実性が増す時代です。売却益を狙うのも、なかなかに難しいかもしれません。そこで「決算時期に保有していれば」受け取ることができる配当金を狙うことを検討します。
しかし、不確実性が増すのは日本企業も同じです。そもそも配当金とは、企業が事業活動を通して得た利益が原資となっています。
今のところは増配をする企業も多いようですが……高配当企業や増配企業に加えて、もう一つ選択肢が欲しいですね。
J-REITという選択肢
| 時期(2025年) | 上昇率・利率 | |
|---|---|---|
| 消費者物価指数 | 5月 | 3.5% |
| 新窓販国債2年償還 応募者利回り |
6月債 | 0.71% |
| 日経平均株価 配当利回り |
6月19日現在 | 2.20% |
| J-REIT分配金利回り | 5月 | 5.02% |
不動産を投資対象とするJ-REIT。その分配金の原資は、投資先の不動産の「家賃や地代など」です。
また、J-REITの物件の多くは国内に所在しています。冒頭で述べた海外の不確実性に対し、企業と比べれば影響は小さそうです。
もちろん、一口に家賃や地代といっても、入居者はさまざまです。もし入居者が企業なら、海外の不確実性と無縁とは言い切れません。
では入居者が個人、つまり賃貸住宅なら海外の不確実性とは無関係なのでしょうか? いいえ、個人が勤めているのが企業なら、海外の不確実性の影響がゼロとは言い切れません。
では、なぜJ-REITが選択肢に挙がるのでしょうか?
次号では、J-REITについて深掘りしてみたいと思います。