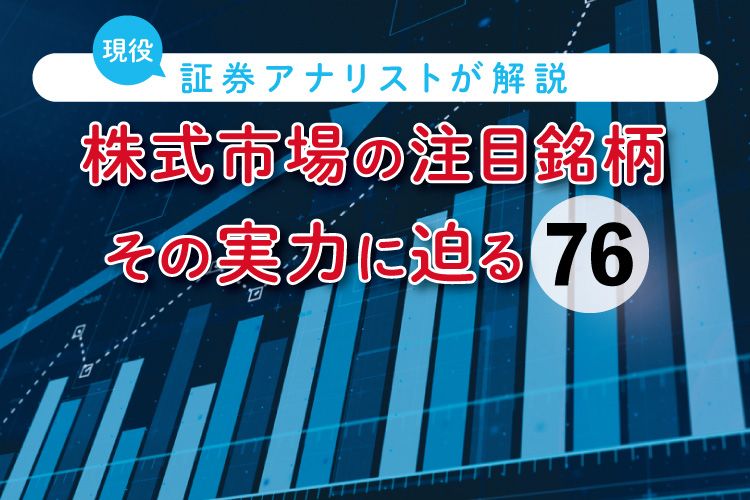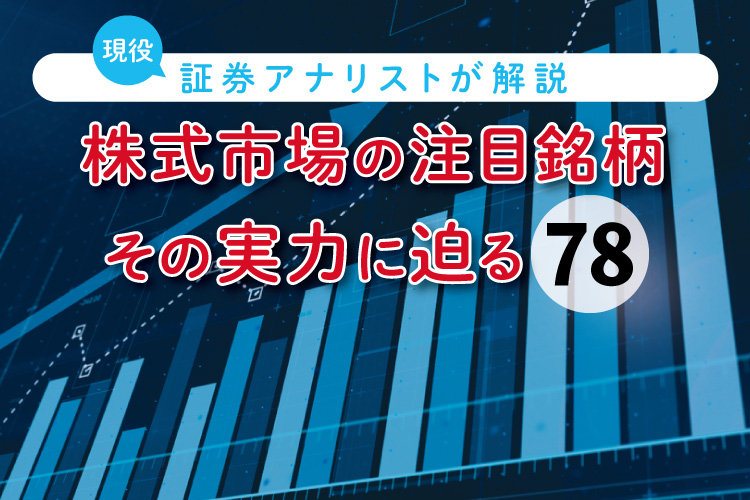700人以上所属する日本放送作家協会(放作協)がお送りする豪華リレーエッセイ。テレビ、ラジオ、動画配信も含めて様々なコンテンツの台本や脚本を執筆する放送作家&脚本家、そして彼らと関わる様々な業界人たち・・・と書き手のバトンは次々に連なっていきます。ヒット番組やバズるコンテツを産み出すのは、売れっ子から業界の裏を知り尽くす重鎮、そして目覚ましい活躍をみせる若手まで顔ぶれも多彩。この受難の時代に力強く生き抜くユニークかつリアルな処世術はきっと皆様の参考になるはず!
連載第211回は、開運アドバイザーとしても大活躍の愛新覚羅ゆうはんさんが再登場。お名前のルーツについての反響が多かったので……。
愛新覚羅ゆうはんさんの前回のエッセイはこちら⇩
愛新覚羅氏の末裔は世界中に100万といる
 愛新覚羅ゆうはん
愛新覚羅ゆうはん作家・開運アドバイザー(占い・風水師)
日本放送作家協会会員
「愛新覚羅」=「ラストエンペラー」だけではない。
なんなら愛染カツラでもない。
希少生物でも天然記念物でもない。
「愛新覚羅」氏は名ばかりが目立つが、満洲族であり女真族である。
女真族は満洲族の中核を成すツングース系民族で、1583年に愛新覚羅ヌルハチ(元は女真族)が女真族の各派を統一し、八旗制度を創設し、満洲語を作り、1635年に民族名を「満洲」に改称。女真は私の出身、黒龍江(アムール)が本拠地なのだ。
中国国内に満洲族はおおよそ1000万人いる。
そのうち100万人ほどが愛新覚羅氏の末裔と言われている。
皇帝や皇帝の親族たち、貴族たちは一夫多妻、沢山の子孫を残すことも仕事だ。国立国会図書館にも収蔵されている「愛新覚羅宗譜」は31冊にも及ぶ。
そのうちの一人が私だ。
なので、珍しくない。
日本でたとえていうなら、“同族の鈴木さん”が100万人いる……みたいなことだから。
そこから細かく、直系か傍系かで分かれるわけだが、我が家は愛新覚羅ヌルハチの第六子愛新覚羅タバイの末裔だ。
愛新覚羅家は太祖であるヌルハチから数えて直系なのか傍系なのかを決める。私はヌルハチから数えて15世代目の直系であり、継承輩字は「燾(TAO)」だ。
また、自己紹介する時は、○○皇帝の末裔とは言わない。
○○皇帝の何子の○○の末裔、または○○親王の末裔というのが正式で、継承輩字を重んじるそうな。
家系図を辿れなければ、愛新覚羅と名乗っていても怪しんだほうがいいというのを研究者方から聞いた。
これは目から鱗だった。
でも、日本にいると「愛新覚羅溥儀・ラストエンペラー」の末裔なんでしょう? と必ず言われるし聞かれる。
その都度「愛新覚羅溥儀には子供がいません。愛新覚羅家は愛新覚羅ヌルハチから数えて……」と解説するのが面倒になり、思い切って愛新覚羅宗譜から出典した個人情報を公式HPに掲載する(家系図あるからそれ見てという)ことにした。
文化人活動している私としては家系図を提示することで、幾分か過ごしやすくなったこともある。
書家でも画家でも作家でも、愛新覚羅氏を名乗って仕事をするのであれば、後ろ盾になる。
それでも、皆様にとって、愛新覚羅=ラストエンペラーなのだ。
一族は膨大で、皇帝の失脚と共に流転の人生を歩んでいくのは、残された親族たちも同様だ。
本当の財宝とは?
先日、NHK放送の映像の世紀バタフライエフェクト「ラストエンペラー 溥儀 財宝と流転の人生」を見た。
わずか2歳で皇帝に即位し、辛亥革命後に退位、満洲國の皇帝となったものの日本の敗戦後に退位。
亡命しようとしたものの、ソ連軍の捕虜となり、中国に引き渡された後は戦犯管理所へ。
釈放後は一般市民として庭師となった。
アイデンティティとはなんだったのか、権力や権威とは、強く考えさせられる記録でありドキュメンタリーだった。
中華最後の王朝「清王朝」の崩壊後、玉座に皇帝がいなくなれば同族たちもまた似たような運命を辿るのだ。資産があればあるほど、地位が高ければ高いほど、粛清は強烈である。
溥儀は紫禁城から持ち出した国宝の数々を売りながら、生き長らえていく。
ひとつ、またひとつ、と命を繋ぐように龍の手から宝珠が放たれていった。
全ての宝珠がなくなった時、龍は人となったと思うと切ない。
 清王朝の国旗。清王朝の崩壊後、資産や地位があればあるほど、皇帝の同族たちへの粛清は強烈だった
清王朝の国旗。清王朝の崩壊後、資産や地位があればあるほど、皇帝の同族たちへの粛清は強烈だった時が流れ、その財宝が世界的なオークションに出品される。
溥儀の財宝だけではない、満洲皇族・貴族たちの財宝もまた流れる。
もちろん、我が家もいろいろあった。
これに関して語るにはまだ時期ではないと思うので、いつか本に仕上げようと思っている。
映像で見る財宝の数々は素晴らしいものばかりだ。
でも、ふと、本当の財宝を授かっていることに私は気づいてしまった。
生き残った親族や同族たちが激動の時代を乗り越え、今でも歴史を引き継ぎ紡いでいることだ。
末裔たちが、今どこで何をしていて、どう生きているかも重要点であり、大切な先祖孝行だと私は思う。
命あるかぎり、先祖に恥じないよう、どう生きるか。
次回は門前日和さんへ、バトンタッチ!
放送作家の地位向上を目指し、昭和34年(1959)に創立された文化団体。初代会長は久保田万太郎、初代理事長は内村直也。毎年NHKと共催で新人コンクール「創作テレビドラマ大賞」「創作ラジオドラマ大賞」で未来を担う若手を発掘。作家養成スクール「市川森一・藤本義一記念 東京作家大学」、宮崎県美郷町主催の「西の正倉院 みさと文学賞」、国際会議「アジアドラマカンファレンス」、脚本の保存「日本脚本アーカイブズ」などさまざまな事業の運営を担う。