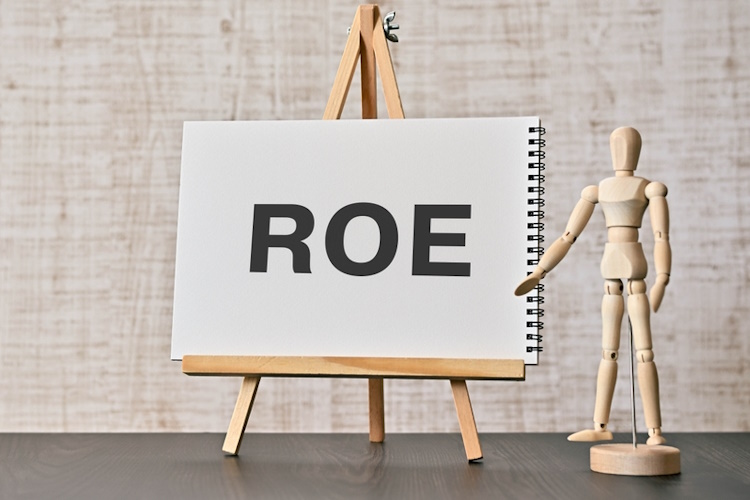文化の壁を超える方法は自己開示と相互理解、もうひとつは……
言葉の壁だけでなく、文化背景の違いもあってコミュニケーションも難しそうです。
陳さん 確かにマネジメントは難しいと感じています。いくら英語ができたとしても、相手のカルチャーを理解できていなければ、どうしてもコミュニケーションのロスが発生してしまいます。
私は海外の大学を卒業して、英語力には自信があったのですが、実際にビジネスを通じていろいろな国の方と接してみると、国ごとの文化の差を感じさせられる場面が数多くありました。
たとえば、相手に対してネガティブなフィードバックをしなければならない場面があります。それを直接的な言葉で伝えるか、間接的に伝えるか、その人の文化によって大きく分かれます。ある書籍では、日本が極端に間接的で、逆に最も直接的なのがオランダ。アメリカが真ん中くらいだと書かれていました。
私の会社には30カ国ほどのメンバーがいて、確かにオランダ人は直接的な表現を好むように思います。オランダ人のメンバーとのコミュニケーションで、人によっては自分が攻撃されていると感じたり、相手の意図と異なる理解をしてしまったりということも実際に起きていました。

そうしたコミュニケーションのミスマッチを、どのように乗り越えたのでしょうか。
陳さん 自己開示と、相互理解が大事だと思います。自分の文化やバックグラウンド、コミュニケーションスタイルを自分から開示していくことを、会社として大切にしています。そのために、私たちはオフラインでのコミュニケーションを大切にしています。
エンジニアはフルリモートでの仕事を好む職種ですが、だからこそ私たちは週に2回ほど、メンバーが集まって話す機会を設けています。「ランチ制度」のような仕組みを作って、メンバーが出社したくなるように工夫しています。そこで発生するコミュニケーションを通じて、相手の文化背景が徐々にわかってきます。
相互理解には、相手を理解しようと努めることが必要です。相手からきついことを言われて「攻撃された」と感じたときも、「もしかしたらこれがこの人の『普通』なのかもしれない」と思って、その真意を理解しようという姿勢でのぞむことが大切だと思います。
そのうえで目指すのは、チーム全体の共通の基準として、Sales Marker独自の企業文化を作ることです。基準がないと、自分のこれまでの習慣に沿って話すことになってしまいます。誰もが円滑にコミュニケーションを取れるように、日本式でもアメリカ式でもない、会社としての文化を確立させていければと思います。
日本人だけのチームでは得られないグローバルな視点とアイディア
世界を見渡すと、多様性を大切にするという流れへの反感からか、反DEI(多様性・公平性・包括性)の声が強まっていますが、やはり多様性がある組織ならではの強さ、メリットは大きいのではないかと思います。
陳さん 強さということでは、文化背景の違いによって、いろいろな視点からアイディアが出てくるところが最も大きいと思います。
たとえば人々が毎日使うスマホアプリにしても、国によって流行するサービスも、好まれるユーザーエクスペリエンスも違います。日本人だけで新しいサービスを作ろうと思うと、どうしても単一の価値観の中に閉じこもったようなアイディアになってしまいます。
Sales Markerのサービスをグローバルに展開していくことを考えたら、グローバルな視点やアイディアが必要となります。日本人だけのチームなら、海外の事情を知ろうとすればお金と時間をかけてリサーチをすることになりますが、それぞれの国の状況を肌感覚で理解しているメンバーが集まるチームでは、多様なアイディアが自然に生まれてきます。
私たちとしてはそうした多様な観点を受け入れること、多様な人たちと協力することを、革新的なサービスを生む原動力にしてきました。それがなければ、この会社はここまで伸びていないと思います。

言葉や国籍で門戸を閉ざせば、成長の可能性を狭める
日本では「人材不足」が叫ばれています。海外の優秀な人を迎え入れたいと考えている企業は、どんなことから始めるのが良いでしょうか。
陳さん 私はもともとグローバルなチームを作ることが目的だったのではなく、強いチームを作ろうとしたら必然的にグローバルな人材が集まったという順番でした。グローバルな組織を作ることが、必ずしも企業の課題解決につながるとは限らないと思います。
とはいえ、人手不足を解消したい、組織を強くしたいといった課題があるのであれば、求人を日本語が話せる人に絞ってしまうのは、課題解決の可能性、成長の可能性を自ら狭めてしまうことになると思います。
目線を少し広げるだけで、広い人材市場がそこに現れるかもしれません。言葉の壁があるのなら、たとえばバイリンガルのマネージャーを採用することから始めるなど、まずは最初の一歩を踏み出してみることが必要だと思います。