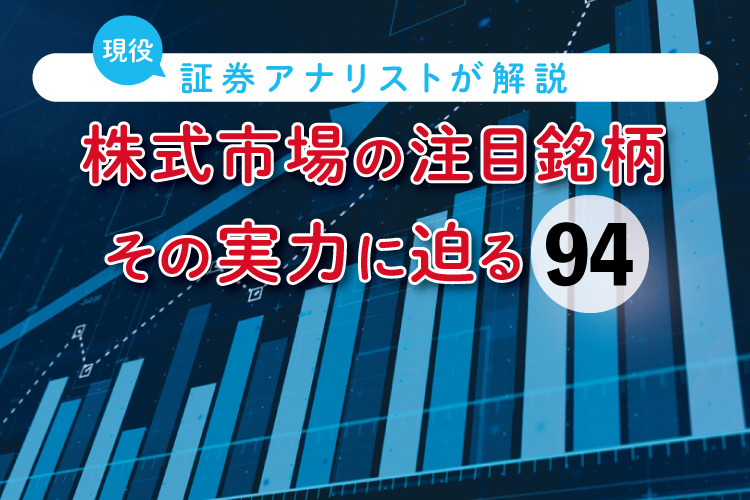現役証券アナリストの佐々木達也さんが、株式市場で注目度が高い銘柄の強みや業績、将来性を解説する本連載。第94回は、魚群探知機や船舶用レーダーなど、船舶用電子機器の分野で世界的に大きなシェアを誇るグローバルニッチ企業、古野電気(6814)をご紹介します。
- 古野電気は世界で初めて魚群探知機の実用化に成功。船舶用レーダーなども手がける
- 売上の約7割が海外。開発力向上のため産学連携型研究にも積極的に取り組む
- 株価は上昇トレンドで、上場来高値をうかがう。PER、PBRに割高感はない
古野電気(6814)はどんな会社?
古野電気は、船舶用電子機器の大手メーカーです。1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功し、現在でも魚群探知機をはじめとする漁船向け機器では世界で40%を超えるシェアとなっています。その後もセンシングと情報処理技術を生かし、船舶用レーダーなどの電子機器を手がけています。
事業構成は主力の舶用事業のほか、産業用や無線LAN・ハンディターミナル事業も展開しています。売上高の約7割が海外向けとなっており、欧州、アジアがそれぞれ約3割、米州向けが約1割です。
同社は、創業者の古野清孝氏が長崎県口之津町に前身の「古野電気商会」を1938年に創業したのが起源です。漁業の近代化のため、日本軍の放出物資の「音響測深機」を改良し、魚群探知機の実用化につなげ、世界の漁法を変えました。その後は漁業用無線機、船舶用レーダー、サーチライトソナーなど、船舶の運航に必要な電子機器を軸に事業を拡大していきました。

古野電気は、漁船や商船など船舶業界で知らない人はいないと言われるグローバルニッチ企業
見えないものを「探る」「測る」「送る」技術力が強み
古野電気の強みは、長年の研究開発で培った技術力です。特に「センシングと情報処理技術、情報通信」の3つの技術を軸に、見えないものを「探る」「測る」「送る」技術を得意としています。例えば「探る」製品の代表格といえる魚群探知機は、海中に超音波を発信し反射波を捉えることにより、魚群の存在や海底の状況を調べることができます。
併せて新規技術の獲得、研究開発のスピードアップなどを目的に、東京大学、京都大学、大阪大学、神戸大学など、数多くの大学・研究機関との産学連携型共同研究に取り組んでいます。
こうした技術力を支えているのが、創業者が創った「現場種技(げんばしゅぎ)」という言葉です。技術開発に行き詰まった時、現場での顧客との対話で新たな開発の種をいかにして見抜くか、それを見抜く感性を大切にするという企業文化も同社の技術力の基礎となっています。
古野電気(6814)の業績や株価は?
古野電気の今期2026年2月期決算は、売上高が前期比0.4%減の1275億円、営業利益が13%減の115億円と、ともに減収減益を見込んでいます。為替の円高が響きますが、一方で商船向け市場は堅調な需要環境が続くと見込まれます。
近年では商船向け電子機器のシェアが上がりつつあり、安定収益となる保守サービスの売り上げが着実な伸びを見せています。また、グローバルのサービスネットワークもかなり充実しています。ITによる機器のモニタリングやソフトのバージョンアップなど効率的なメンテナンスができるのも収益増に寄与します。
7月4日の終値は3740円で、投資単位は100株単位となり、最低投資金額は約38万円です。予想配当利回りは2.9%です。株主優待はありません。

株価チャートは上昇トレンドが続いており、直近で6月の年初来高値3850円の高値圏で推移しています。1984年には4100円の上場来高値を付けており、ここを上抜けると値上がりに弾みが付きそうです。予想PER(株価収益率)は13倍、PBR(株価純資産倍率)は1.6倍と、さほど割高感はありません。
舶用事業ではリモート管理による高品質なサービスの提供、米州を中心としたプレジャーボート向けの戦略商品の展開などを推進しています。また、自律航行支援システムや漁業データ活用クラウドサービスといったモノとデータを組み合わせたビジネスへの投資にも注力しています。
米国のトランプ大統領が自国の造船業復活のため、日本に軍民両用の造船で協力を要請しているのも新たなビジネスチャンスにつながると期待しています。株価についても再評価の余地が大きいとみて、さらなる値上がりに期待したいところです。