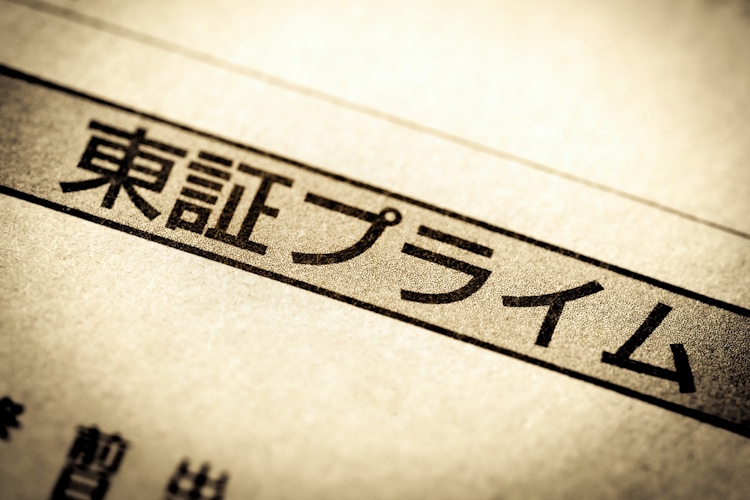大切な家族のため、財産を遺してあげたいという人にとって、税金の問題は気がかりなことでしょう。贈与や相続のときにかかる税金は仕組みが複雑なため、どうするのが家族にとって一番よいか分からず困っている方も少なくないでしょう。今回は、親から子・孫への贈与・相続する際にかかる税金の基本と、2026年3月まで受けられる非課税措置について解説します。
※本記事では税金の仕組みを簡略化して解説しています。詳細や個別のケースについては国税庁のホームページなどでご確認ください。
- 贈与税は生きている人、相続税は亡くなった人から財産を受けた時にかかる
- 生前贈与や非課税措置の活用で税負担を軽減できる可能性も
- 子や孫にできるだけ多くの財産を残したければ、渡し方にも工夫が必要
贈与税と相続税の仕組みと違い
贈与や相続は「身内や家族にお金をあげる」という似た行動ですが、それぞれにかかる税金に違いがあります。
贈与税の種類としくみ
生きている個人から財産を譲り受けた際にかかるのが、贈与税です。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、それぞれ税金の計算方法に違いがあります。なお、どちらの方法でも110万円の基礎控除(税金計算の対象にならない金額)が適用されます。
暦年課税:1年間に受けた贈与額の合計を基準に税金の計算を行う方法です。その年の1月1日から12月31日までに受け取った額が基礎控除を超えた場合、その金額に対して10万円~400万円(ただし、未成年者が成人の父母・祖父母などから贈与を受けた場合は640万円まで)の控除が適用され、10%~55%の税率で税金が計算されます。
相続時精算課税:1年間に受けた贈与額の合計を基に贈与税を計算し、財産を譲った人が亡くなった時に相続税として精算する方法です。対象となるのは、原則60歳以上の父母または祖父母からの贈与です。基礎控除を超えて受け取った金額の合計が2,500万円までであれば贈与税はかかりませんが、それを超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。贈与税がかからなかった場合でも、財産を譲った人が亡くなった時点までに受け取った金額は、相続税の対象として再計算されます。
贈与を受けた人は、これら2つの課税方法のどちらかを選択できます。
ただし、一度相続時精算課税を選択すると、その後暦年課税に切り替えることはできません。
相続税のしくみ
相続税は、亡くなった人の財産(以下、遺産)を相続した際にかかる税金です。受け取った遺産を基準に税金が計算され、3,000万円+600万円×法定相続人の数までが基礎控除の範囲です。遺産額がこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
この基礎控除の金額を超えた遺産がある場合には、その超えた分に対して10%~55%の税率と50万円~7,200万円の控除が適用されます。また、相続をする人の年齢や障害の有無など、特定の条件に該当すると控除が加算されることもあります。
贈与・相続税の負担を軽減させる方法はあるの?
贈与や相続を考える人にとって気になるのは、これらの税金を軽減させる方法についてですよね。それぞれの税金を軽減させるために取れる手段の一例をご紹介します。
生前贈与を行う
相続税の負担を軽減する方法として挙げられるのが、生前贈与です。
遺産としてまとまった額を相続した場合は相続税の対象となります。そのため、毎年110万円の基礎控除の範囲内で贈与を行い、将来相続税がかかる遺産額を減らすことで、結果として税金の負担を軽減できると言われています。
しかし、手渡しでの現金やり取りなどは贈与と認められないケースもありますので、贈与契約書の作成や銀行振り込みなど記録の残る方法を取るなどの対策が必要です。また、相続が開始する前の3年間に行われた贈与は「生前贈与加算」の対象となり、その金額が相続財産に加えられ、相続税の計算に含まれることになる点にも注意が必要です。
教育資金の一括贈与非課税措置を活用する
贈与税の軽減には、教育資金の一括贈与に係る非課税措置が活用できる例もあります。この制度は、祖父母・父母から30歳未満の子・孫に教育資金を一括で贈与すると、最大1,500万円が非課税になります。
金融機関と契約して専用の口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出することで制度を利用できます。贈与を受けた後、口座からお金を引き出す際には、学校の授業料や習い事など、教育資金として使ったことを証明するための領収書を金融機関に提出する必要があります。
この制度の注意点としては、2026年3月31日までの期間限定の措置であること、贈与を受けた子・孫が30歳になった時点、または契約期間中に贈与者が亡くなった場合に、使い切れなかった残額に応じて、贈与税や相続税が課される可能性があります。
 子や孫に財産を残したければ、渡し方にも工夫したい
子や孫に財産を残したければ、渡し方にも工夫したい将来の家族のためにお金の渡し方を考えてみて
子どもや孫など、大切な家族のために財産を取っておきたいという気持ちはとても大切です。
しかし、なるべく多くの財産を受け渡すためには、ただ大きな金額を用意するだけでなく、どんな渡し方をするかなどにも工夫が必要です。
財産形成と併せて、こうした制度についてあらかじめ調べておき、どうするのがより家族のためとなるか、考えてみるのが良いかもしれませんね。
出典URL
- 国税庁「財産をもらったとき」

- 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

- 国税庁「財産を相続したとき」

- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」

- 国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

- 全国銀行協会「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度?」