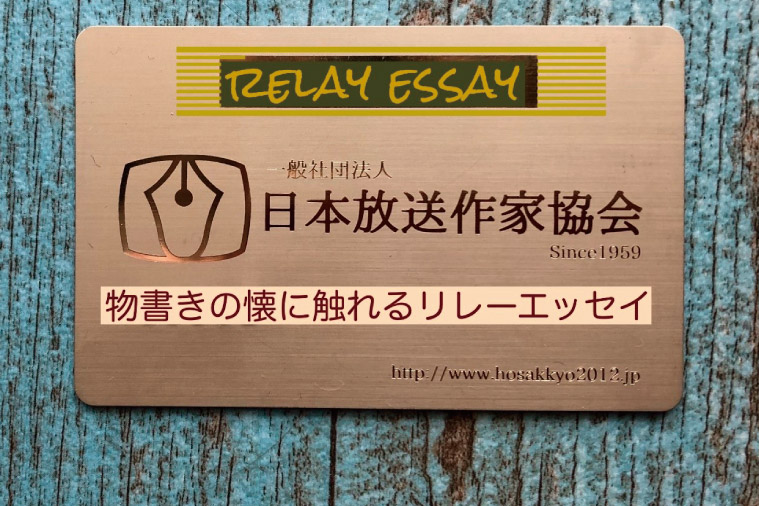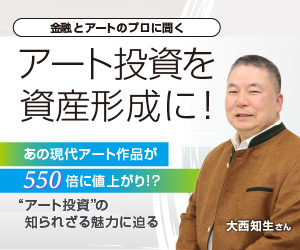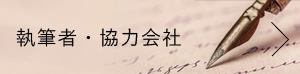700人以上所属する日本放送作家協会(放作協)がお送りする豪華リレーエッセイ。テレビ、ラジオ、動画配信も含めて様々なコンテンツの台本や脚本を執筆する放送作家&脚本家、そして彼らと関わる様々な業界人たち・・・と書き手のバトンは次々に連なっていきます。ヒット番組やバズるコンテツを産み出すのは、売れっ子から業界の裏を知り尽くす重鎮、そして目覚ましい活躍をみせる若手まで顔ぶれも多彩。この受難の時代に力強く生き抜くユニークかつリアルな処世術はきっと皆様の参考になるはず!
今回は、連載第202回にして2025年最初の一本。放送作家・コラムニストの山田美保子さんにご登場いただきました。
放送作家を辞めようと思った

山田美保子
放送作家、コラムニスト
日本放送作家協会会員
「僕たちは出入り業者なんですから、“お呼び”がかかっている間は続けていていいんじゃないですか?」
とは、今から25年程前、『恋のから騒ぎ』(日本テレビ系)で御一緒していた放送作家の大先輩、廣岡豊さん(以下、廣岡先生)からいただいた“珠玉の言葉”である。
ちなみに、どういうシチュエーションだったかというと、イレギュラーで生田スタジオでの収録となり、たまたまマイカーでいらしてなかった廣岡先生を私のクルマにお乗せして、当時、毎収録後、明石家さんまさんが開催してくれていた食事会の現場=『游玄亭』へ向かう車中だった。
30歳になってから放送作家と同時に雑誌のライターも始めて10年程が経ち、いわば“二刀流”だった私は、テレビ業界のことも紙メディアのことも知っているという理由から双方で高い下駄を履かせてもらっていた。
振り返れば、間違いなく「女は得」な時代だったし、“女性誌創刊ラッシュ”や“女性エッセイストブーム”に乗っかり、既に多数の連載を抱えていた。
一方、放送作家は男性ばかり。特にバラエティとなると女性は本当に珍しく、いまの“脳”で考えたらセクハラだらけの日々だったようにも思う。
出版社とて“男性社会”には違いなかったが、ライター仲間の女性たちがたくさん居たし、女性誌なら女性編集者の数のほうが多かった時代。正直、居心地がいいのは出版社のほうだったのだ。
で、廣岡先生に上記の話をしつつ、「(放送)作家を辞めようと思っているんです」と告げたところ、冒頭の返答をいただいた。
「なんでもやるなぁ」は褒め言葉
『恋のから騒ぎ』でも女性の作家は番組開始から終了まで私一人だったし、廣岡先生をはじめ大御所の作家さんばかりの中で私は「小姑」という肩書を与えられ、アラフォーになってもギャルのような扱いだった。
それでも、いつも丁寧語で話してくださっていた廣岡先生との会話はいつもストンと心に落ち、ジンワリ沁み入ったものだ。
以来、「お呼びがかかっている間は続けていい」は私の“座右の銘”にもなり、自分では「ちょっと違うかな?」「私ではないんじゃないか」という仕事でも、オファーをいただいた場合、100%受けてきた。「もう少し仕事を選べよ~」とか「なんでもやるなぁ、山田美保子」は褒め言葉だと捉えている。
 自分では「ちょっと違うかな?」「私ではないんじゃないか」という仕事でも、オファーされれば100%受けてきた
自分では「ちょっと違うかな?」「私ではないんじゃないか」という仕事でも、オファーされれば100%受けてきた肩書にしても「トレンドウォッチャー」とか「芸能コラムニスト」とか、自分の意に反する呼ばれ方をすることも少なくないが、そのように紹介してくれる番組や雑誌に対してはなるべくNOとは言わないようにしている。
果たして、「ずっと第一線で活躍している」「テレビでも雑誌でもこんなに長く仕事をしている人は他にいない」と業界関係者から言ってもらうことも多いが、その根本にあるのは、あの日、廣岡先生が言ってくださった言葉なのだ。これ……、決して“業界”だけの話ではないように思う。そして当然、やり遂げた仕事の傍らには“報酬”がある。
今年の5月で68歳。「なんで、こんなに働いてるの?」と自分にツッコミを入れつつ、オファーがある限りは仕事を続けるつもりだ。
“お金”への感謝を忘れずに……。
次回は青木ドナさんへ、バトンタッチ!
放送作家の地位向上を目指し、昭和34年(1959)に創立された文化団体。初代会長は久保田万太郎、初代理事長は内村直也。毎年NHKと共催で新人コンクール「創作テレビドラマ大賞」「創作ラジオドラマ大賞」で未来を担う若手を発掘。作家養成スクール「市川森一・藤本義一記念 東京作家大学」、宮崎県美郷町主催の「西の正倉院 みさと文学賞」、国際会議「アジアドラマカンファレンス」、脚本の保存「日本脚本アーカイブズ」などさまざまな事業の運営を担う。