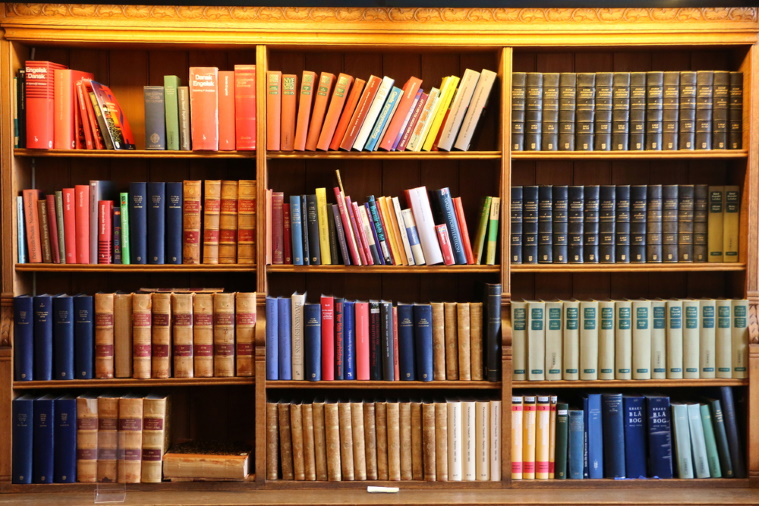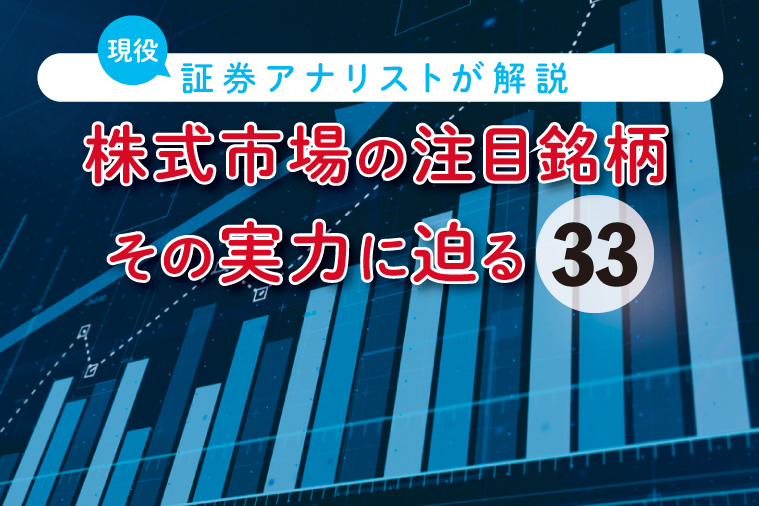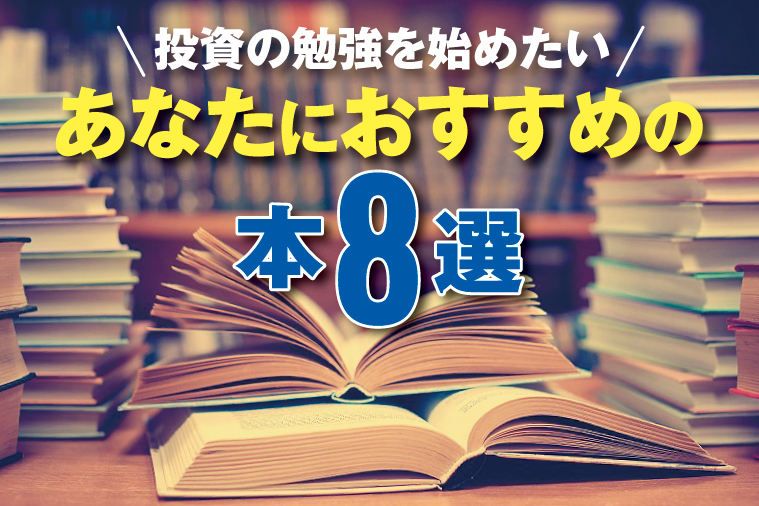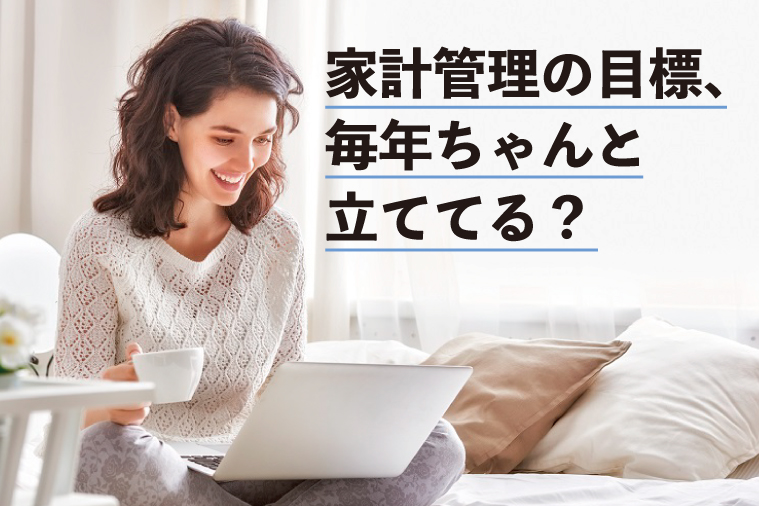宮崎県延岡市で保険業や資産運用のアドバイスに携わる小田初光さんが、地方で暮らす生活者のリアルな視点で、お金に関するさまざまな疑問に答えます。今回のテーマは「利回り」。昨今のインフレを反映して預金金利が上がっており、定期預金の金利も魅力的に映りますが、それが果たしてインフレへの備えになるのでしょうか? インフレと利回りの関係について解説します。
- 2020年と比べて円安になり株価は上昇したが、政策金利は大きく上がっていない
- インフレの怖さはお金の価値が減ること。定期預金の金利では物価上昇率に及ばない
- インフレリスクに打ち勝つには賃金アップか、リスク商品を運用するしかない
金利が上がってこそ本当のデフレ脱却
【質問】
こんなに物価も上がってきてたいへん。お金を増やすのにはリスクは当たり前のことじゃけど、金利も上がってきたから、定期預金も良いちゃないですか? 安心、安全パイだし。
ようやく金利がある日本に戻ってきています。それも約30年ぶりです。ただし、金利は一気に上がるのではなく、じわりじわり市場に反映しながら時間を要しながらになるでしょう。
約5年前(第24回相談室)に、預金で増えない時代の資産運用は金利ではなく「利回り」で考えようと書かせていただきました。ズバリ、運用商品の選び方の基準を「複利運用効果」として、運用のリスクと向き合うことを学び、覚えておくためです。
感慨深いのは、2020年時点ではNISAが始まって6年もたっているのにも関わらず、口座開設がいまいち盛り上がっていない状況であったのに対し、2024年に新NISAが始まった今では、成人の4人に1人が口座開設するほどの活況になっていることです。
当時は私も、NISAの活用を主体に見ていなかったのを覚えています。2020年9月当時の日経平均株価は約2万3000円、基準金利(政策金利)約0.3%、対ドルの為替レートは約105円でした。日本は株価を上昇に、為替を円安方向に誘導する政策に特化していました。
私もその頃、「今後は、急なインフレによる物価上昇が起きない限り、今のゼロに近い金利水準が上がることはない」とコメントしています。
そして今、金利の切り上げをインフレ(?)によって、ようやく行い始めたということになりますが、自民党新総裁誕生もあり、2025年10月7日現在の日経平均株価は約4万8000円、基準金利0.5%、為替約152円と、円安進行と日経平均株価の上昇になっています。
問題は基準金利の上昇が思ったより伴っていないというジレンマで、金利が上がる環境にもあるに関わらず、上げられない状況の中です。
金利は米国の景気がどうなのかにもよることになりますが、必ず金利は上がり続けていき、そうなって初めてデフレ脱却となることでしょう。
今回からはNISAの活用を念頭に、資産運用に重要な「金利」と「利回り商品」について今一度検証していきます。
定期預金の金利はこの5年で大幅アップしたが……
まずは「金利」のリスクについて、今一度紐解きます。
例えとして、2020年当時に銀行で100万円の定期預金をした場合の金利(利息)を基準に、さまざまなリスク商品について考えています。2025年10月現在、商品群の「利回り」はどうなっているのか?
100万円を1年間銀行に預ける定期預金の儲けが、ネット銀行でようやく5500円ほど(金利0.55%の場合、税引き前)出るようになった現在、リスク運用など考えていない方からすれば、2020年当時の0.002%(20円)から、0.55%(5500円)に儲けが増えたのですから、大きなステップアップです。満足度は増していることでしょう。
| 2020年 | 2025年 | |
|---|---|---|
| 定期預金の金利 (100万円、1年) |
0.002% (メガバンク) |
0.55% (ネット銀行) |
確かに数値上では上がっていますが、喜ぶべきことなのでしょうか? タンス預金として家などに多くのお金を抱え込む高齢者、地道な努力が一番だとせっせせっせと働きながら銀行などに預金を持つサラリーマン世代など、いまだに身近に多く見られます。
一方、「お金の使い方がわかっていた方」は、「利回り」を求めながら自己研鑽に勤めてきました。この5年の運用益利回りが合計30%(プラス30万円、NISA活用なら税の支払いがなくまる儲け)ある方もいます。その差は、たった5年ですが歴然とした差となっています。
地道に積んでいく預貯金は、最初から決められた確定金利商品でしかありません。ただ、決められた金利より物価上昇が高くなれば、預貯金(お金の価値)は減ることになってしまいます。これに気づかなかったら大きなリスクとなり、問題なのです。この差に「気づき」がなければ、政治に口だけの不満しか言えない一般人でしかありません。
年3%の物価上昇が続くと、20年後の100万円の価値は?
金融リテラシーの差は「気づき」しかありません。気づかないことは、残念でしかありません。
その「気づき」を完璧なものにするために、物価上昇の怖さ(インフレ経済)を、今一度説明します。
例えば、銀行の1年定期の金利が1%になったとしましょう。100万円預けると、1年後には101万円になります。しかし、物価が1年で3%上昇すると、現在の100万円で買える物やサービスの値段が、1年後には103万円出さないと買えなくなります。すなわち、定期預金のお金は利息で増えても、お金の価値は1年前より目減りしたことになります。
定期預金でこれですから、普通預金、タンス預金だったらと考えるとゾッとしてしまいます。
また、普段何気なく買っているお菓子など、以前より少なくなっていませんか? 価格は据え置きでも、中身を減らすなどといったことが起きています(ステルス値上げとも言われます)。消費者物価指数を見ても4年間で合計約10%上昇しているところを見ると、これから物価上昇が続いていくと考えた方がいいでしょう。
仮に100万円のお金があったとして、現在のインフレ率が約3%付近なので、3%の物価上昇が続いたとしたら、20年後そのままにしていた100万円のお金の価値は、今の基準でいくらになるでしょうか?
答えは約55万円。ほぼ半減してしまうことになります。
今年に入り、日本銀行が追加利上げを決定して政策金利を0.5%にしました。これを受けて、メガバンクなどの普通預金金利が0.2%に引き上がり、一部ネット銀行などはキャンペーンとして1年定期金利を0.5~1%程度にしています。しかし、今の現状はインフレ率3%であり、たとえ金利が1%になっても、物価上昇にはとうてい及びません。
インフレ対策は賃金に期待するよりリスク商品を使う
政策金利は今後も徐々に上がっていくと考えられます。預金金利とインフレ率の差である2%以上を埋める、つまりインフレリスクに打ち勝つ手段は、2つの方法しか考えられません。
1つは賃金アップです。少なくとも給料が毎年2%以上上がり続けていくことが必要になりますが、最近のニュースで、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると働く人1人当たりの現金給与総額が前の年の同じ月から1.5%増えたが、物価変動により、実質賃金は8カ月連続でマイナスとなったと報道されました。マイナスでは話になりません。インフレに打ち勝つほどの賃金アップを期待するのは厳しいといえるでしょう。
そしてもう一つの対策が本命となりますが、インフレ対策には、インフレに強い株式などに焦点をおきながら、リスク商品を資産に組み入れる運用しかありません。
5年前から比較しても、インフレリスクへの「気づき」があった人と、そうでない人には大きな差となっています。これからはさらに差が開いていくので、自分磨きを忘れずに次回は「利回り商品」を詳しく見ていきます。