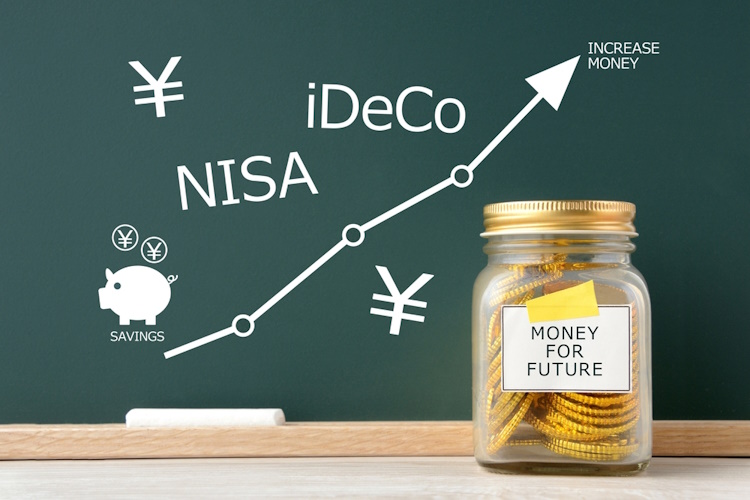宮崎県延岡市で保険業や資産運用のアドバイスに携わる小田初光さんが、地方で暮らす生活者のリアルな視点で、お金に関するさまざまな疑問に答えます。今回は、NISAやiDeCoで資産形成を始めたいと思いながらも、何を買っていいかわからないと悩む30代の女性からの相談に対して、運用の中心となる金融商品「投資信託」の特徴と利点についてお話しします。
- 預貯金すらしづらい現状では、ライフプランの立て方と、投資による資産運用が重要
- 個人でも小口で分散投資ができる投資信託は、資産運用において有利な金融商品
- 良い投資信託を選べば、長期的に定期預金を大きく超えるリターンが期待できる
「安全・確実」一辺倒の資産運用は成り立たない
【質問】
NISAやりたいんですよ。iDeCoもやりたいんですよ。でもどうすればいいのかわからないんです。何を買えばいいのかわからんし、どこに行けば良いじゃろうか?
30歳代の女性が発した言葉です。都市部にお住まいの方からすれば、今頃何言ってんだよ~?と思われるでしょう。SNSなど運用の情報源は山ほどあるのに、地方では今でもこれが現実です。
私がマネー相談をウェブサイトで始めてから5年超経ちますが、このような相談が後が絶たないほどあります。国が思っているよりはるかに、地方では根っこは厳しいのが実情です。金融リテラシーのなさが大きな要因になり、マネー相談に拍車をかける結果にもなっています。
その相談の大半が女性で、特に家計を担っている主婦層は日頃からお金を扱っていることで将来への危機感が強いとも言え、好き勝手やってる?旦那はお金に無頓着がことが多いのです。
それはそうです、働き、そして対価として賃金をもらい、そして消費をしていき、残れば預貯金となりますが、今はその預貯金もできない生活になっている現実があります。自分たちのライフプランを、キャッシュフロー表など使って立てていかないと、お一人様ならともかく、ファミリーともなると、子供・持ち家の出費で一発破綻に追い込まれていきかねません。
預貯金しか知らない国民性と、長年続いた日本経済の高度成長期に培われた人生設計で狂いがなかった幸せな時代の習慣は、簡単に変えられません。しかし、とうに高度成長は1980年代のバブル崩壊で終焉しています。財産づくりは「安全確実」一辺倒では、もう済まされません。高度成長期から成熟経済となった日本では、個人も「自立経済」の生き方をしていくしかありません。
そのための運用ということで、リスクを取ってリターンを得る資産運用を積極的に活用していこうと、国が制度面から後押しをして進めています。
今回は原点に戻って、NISA、iDeCoの基本となる投資信託について、投資初心者に合った購入方法を数回のパートで考えていきます。
なぜ投資信託は個人の資産運用で有利なのか?
相談者には、まずは投資信託への理解を深めていくことが最初のステップだと言っています。
NISA、iDeCoなどはあくまで、儲かった利益にかかる税金をタダにするための活用法であり、利益が出なければ、投資信託もただ損するだけのリスク商品になります。マイナス運用では何もなりません。
ここ10年は右肩上がりの上昇相場で運用商品全般に利益が出ていますが、下落相場となると、商品の特徴がわかっていなければ、下がった商品をどうしていいかわからなくなり、行き当たりの人任せになってしまいます。

下落相場になったときに迷ってしまい、判断を間違えてしまえば、資産運用はうまくいかなくなる
もちろん株式投資も運用商品(銘柄)のひとつになりますが、初心者には株式投資よりも投資信託が適しているという理解を深めていくことにしましょう。投資信託が資産運用にこんなにも有利なんだと理解できれば、商品を知る努力もするし、運用の責任も持つこともできます。
投資信託は、元々は英国生まれで、普通の個人やサラリーマン家庭が財産づくりをするためのツールとして世界中で普及してきたもの。いわゆる小口投資家の共有財産です。
例えば、小口資金でどんなに頑張っても、株式投資の個別銘柄ではたいした投資はできません。理由は資金が少ないからで、日本の株式投資なら数万円程度のお金ではせいぜい1銘柄~3銘柄しか買えません。安全重視の銘柄を選択したつもりでも、その中で自分が買った銘柄が破綻などすれば、投資収益はお先真っ暗、大きくマイナスになります。つまり、小口資金で個別銘柄を運用しても宝くじを買うようなもので、当たる確率も低くなります。
ところが投資信託なら不特定多数の投資家から資金を集めることができるので、投資家の資金が小口であっても、全体では大きな資金量となります。その資金で100銘柄ぐらい組み入れれば、たとえ1社が破綻したとしても99社の銘柄が補い、そして景気の流れに乗れる確率も高まります。それだけ投資収益を得られる機会も増えていきます。
良い商品を選べば、定期預金よりはるかに高いリターンが期待できる
私の経験で、長期でしっかり運用する投資信託の場合は10年~20年単位で保有すると、定期預金よりもはるかに高いリターンが出ます。
定期預金は、契約時の金利で満期まで得られるリターンが決まります。地方銀行など、今でも5年預けて年0.35%ぐらいにしかなりません。これが5年間も続くのかと思うとゾッとします。高金利時に高金利商品で運用することはあっても、低金利時にはリターンが得られる商品にシフトしたりと、柔軟な発想が必要になります。
投資信託の運用者は、今の時代に適した株式投資中心のポートフォリオを創り出して、長い期間をもってトータルで100%、200%と、定期預金よりもはるかに高い運用益を目指していきます。
それでも運用成績が悪ければ、それはそれで投資信託運用者の問題であると言えます。さっさと乗り換えるのが懸命の判断ですが、今も通算で2倍以上のパフォーマンスを出し続けている投資信託が多く存在していることがわかれば、商品に興味を持ち、調べることにつながるはずです。10年定期を始める感覚で、商品を調べてみるだけで十分な行動となります。
投資信託にペイオフはなく、金融機関が破綻しても資産は保護される
最後に、投資信託はペイオフ(預金保険制度)とは関係なく、心配ご無用なこともお伝えします。
金融危機が起きて銀行が融資を回収できなくなるなどすれば、預金者から預かった資金の一部は返済不能になります。だから「預金や定期預金も1000万円までは保証しましょう。それ以上はお約束できません」というのがペイオフの制度です。
ところが投資信託は、投資家の資産は信託銀行が受託資産として管理するだけです。信託銀行は、預金や定期預金のように信託銀行が借入金として融資などにまわすことは一切できません。信託銀行の経営が行き詰まっても、運用資産が返済不能になることは絶対にありませんし、全額保護されます。
今は1つの金融口座に多額の資金を置いていないから関係ないと思われがちですが、老後資金不足問題から、先々は金融機関に預けるお金が増える可能性が高まっていますので、あながち関係ない話ではないかもしれません。投資信託においては、これは安心材料になります。
次回は、今から始める投資信託の選別とNISA、iDeCoでの購入法について深掘りしていきます。