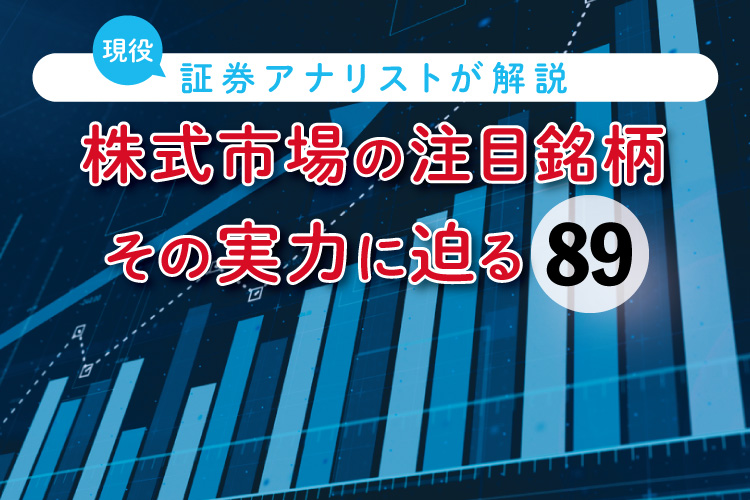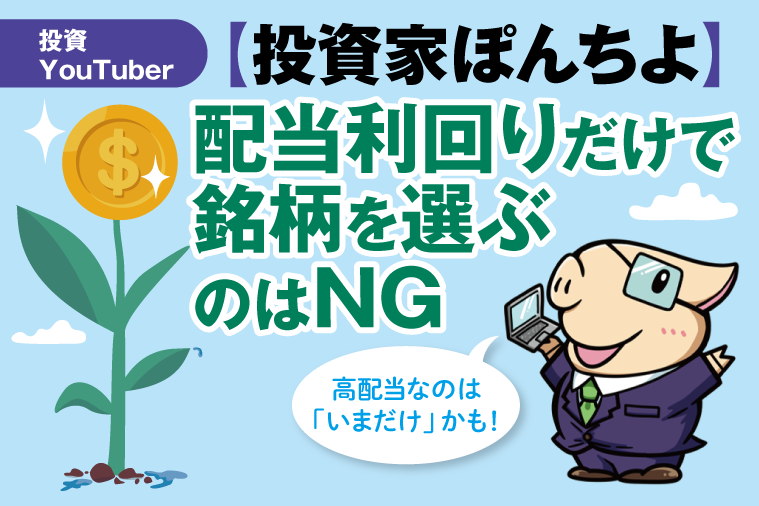宮崎県延岡市で保険業や資産運用のアドバイスに携わる小田初光さんが、地方で暮らす生活者のリアルな視点で、お金に関するさまざまな疑問に答えます。今回は、金融機関でNISAを勧められた相談者が「ETF」という金融商品に対して抱いた興味と疑問に対して、つみたてNISAでETFを活用する可能性について探っていきます。
- 銀行でETFを勧められないのは、証券会社でしか取り扱えない金融商品だから
- 低コストがメリットのETFは分配金の扱いに注意が必要。自動で再投資ができない
- ETFは基本的に定額・自動で積立投資ができないため、初心者には扱いが難しい
金融機関がつみたて投資枠でETFを勧めない理由
【質問】
新NISAのつみたて投資枠で積立投資するために金融機関に足を運んだのですが、いくつかの投資信託商品の説明だけで、他の商品説明はありません。NISA制度のチラシにはETFとかも積み立てできると書いていますが、ETFって一体、何もんですか?
今回も引き続き、新NISAの活用を始めた方が「何」枠で購入したのか? そして、積立投資を始める方法を「何」にしていくのか? を紐解いていきます。
前回は「つみたて投資枠」についてのメリットを話しましたが、今回の相談者のように、NISA制度の説明チラシに書かれている「ETF」という商品を気に留める方もいます。
ETFとは別名「上場投資信託」と言われる商品です。字のごとく、東京証券取引所などの金融商品取引所で取引される、上場している投資信託です。株式投資と同じような取引ができる商品と思ってください。
ここで疑問に思う方もいるかもしれません。なぜ相談者は、金融機関でETFを勧められなかったのか? 積み立て運用ができる商品だったら何かしらメリットがあるはずなのに、教えてもらえないのはなぜか? そんな疑問が湧いてきます。
名前からして同じ「投資信託」なのだから、悪い方に考えるなら「(投資家にとって)良い商品だけに、金融機関は(あまり儲けがないから)勧めたくないのか?」など、何か裏がありそうに感じますね。
でも答えは簡単、購入してほしくても「売れない」だけです。ETFと一般の投資信託では、購入できる金融機関が違うことがその理由です。ETFは銀行からは購入できません。
金融機関の中でも、株式などを売買可能な時間帯にその場で売買できる仕組みを持つ証券会社にNISA口座を持たなければ、NISAでETFを買うことができません。逆に言うと、NISA口座は1人1つしか持てないことから、銀行にNISA口座があれば、つみたて投資枠でも成長投資枠でもETFは活用できません(証券会社のNISAではない他口座であれば売買可能)。
だから銀行では勧めてもらえないわけです。
だとしたら、ETFは購入するためのハードルが高くなるのではとお思いかもしれませんが、株式投資の経験者であれば、ETFは比較的簡単に取引できます。
このことから見えるのは、NISAのつみたて投資枠は初心者向けの枠ですが、つみたて投資枠でETFを利用するのは経験者向けであるということです。勉強も必要であると言えます。
商品数からしても、2025年7月28日付けで東証のETFが全部で366本あるのに対して、つみたて投資枠の対象商品はわずか8本の指数連動型(うち1本は東証ではなく米国市場に上場するETF)と圧倒的に少なく、選びやすくはなっています。ETFでもドルコスト平均法(高い時に少なく、安い時に多く買うことで平均購入単価を下げられる)のイメージがまさに実践できますので、1つの商品として選択になるでしょう。
とはいえ、初心者にはなじみが少ないETFには、投資するにあたり注意点があります。
つみたて投資枠のETFの特色と注意点
ここからは、ETFの商品を見ながら、その特色や注意点について検証していきます。
つみたて投資枠のETFはコストが低い
つみたて投資枠で投資できるETFの特徴として、コストが安価なことが挙げられます。
対象となる指数も金融庁から指定された指数に限られ、証券会社にかかる売買手数料は1.25%以下、信託報酬は0.25%以下などの条件があります。成長投資枠で投資できるETFは300本弱あるので、つみたて投資枠に選ばれたETFがいかに少ないかがわかります。
| 銘柄名 | 信託報酬 | 運用会社 |
|---|---|---|
| iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 0.03%※ | ブラックロック・ ファンド・アドバイザーズ |
| iFreeETF JPX 日経400 | 0.18% | 大和アセットマネジメント |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 0.06% | 大和アセットマネジメント |
| iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.12% | 大和アセットマネジメント |
| 上場インデックスファンド 米国株式(S&P500) |
0.15%程度 | 日興アセットマネジメント |
| 上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 |
0.24%程度 | 日興アセットマネジメント |
| 上場インデックスファンド 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) |
0.24%程度 | 日興アセットマネジメント |
| 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) |
0.24%程度 | 日興アセットマネジメント |
※海外ETFのため、経費率を掲載
つみたて投資枠のETFの分配金における注意点
ETFを購入する上での注意点に、分配金の受け取り方があります。受け取り方を、株式投資も含めて「株式数比例配分方式」(配当金や分配金を証券口座で受け取る方式)にしておかないと、配当金に税金がかかりますのでご注意ください。
また、より効率よく複利効果を得るためには、分配金などは再投資した方がいいです。ただし、ETFの分配金再投資は投資信託のように自動ではできません。ご自身の手でETFの買い注文を出す必要があるので注意が必要です。
NISAで投資するETFを選ぶポイント
成長投資枠を含んだETFを選ぶ際のポイントをあげるとすれば、
①運用コスト(信託報酬の低さ)
②流動性(市場でどれだけ活発に売買取引が行われているか)
の2点です。
ETFは売りたい人、買いたい人がマッチングしてはじめて取引できます。リアルタイムの株式取引と同じで、流動性が低いと注文しても取引しにくく、希望のタイミングで売買できない可能性があります。流動性は取引画面などを通じて確認することが可能です。
実際のETFで、つみたて投資枠で活用する是非を考える
今回は、つみたて投資枠の対象商品のひとつである、日興アセットマネジメントの『上場インデックスファンド米国株式(S&P500)』(銘柄コード「1547」)を参考にして考えていきます。
7月29日14時現在で、1口10,330円くらいになっています。最小1万円くらいで買えるということですが、ここで疑問が湧いてくるはずです。
実は、ETFは自動での積立が難しい投資信託なのです。
自動で積立投資をする場合、ネット証券であれば、まずは買い注文画面の「積立」をクリックして画面を表示させます。一般的な取引方法は、株式と同様に指値注文と成行注文が選べますが、ETFの自動積立では、投資信託の積立投資のような「毎月1万円ずつ積み立てる」といった投資が困難な場合があります。
『上場インデックスファンド米国株式(S&P500)』の7月29日の終値は10,320円でした。1単元(取引単位)は1口です。証券会社に支払う売買手数料は無いものとして考えると、1万円ちょうどで買おうとすると買えません。10,330円で買うことになりますので、投資信託のように定額(同じ金額ずつ)で購入するという感覚では、ETFの積立投資はできません。
リアルタイムでの取引を通じて、刻一刻と動く経済を体感できるのもETFの特徴といえますが、1口いくらで買えるかわからないので、極端な話、1か月後には15,000円もありうるし、5,000円もありえます。
一部の証券会社では株式累積投資のサービスを提供しており、ETFでも定額積立投資が可能ではありますが、対象となるETFが限られているなどの制約があり、そもそも現状ではつみたてNISAにおけるETFの扱いそのものが8銘柄のみに限定されています。つみたて投資枠でETFの定額購入は難しいのが現実といえます。
どちらにしても、投資初心者がNISAでETFを活用するには「つみたて投資枠」がベストでも、投資信託を買う場合と比べて手間がかかります。現状でETFは、投資信託で長期積立投資をする「ほったらかし運用」には適しているとは言えません。
成長投資枠を活用する場合や、株式投資の経験者にとってはETFは有効な商品ですが、初心者がつみたて投資枠で長期積立投資を始める場合は、なるべくならETFは選択しない方が良いのではないでしょうか。