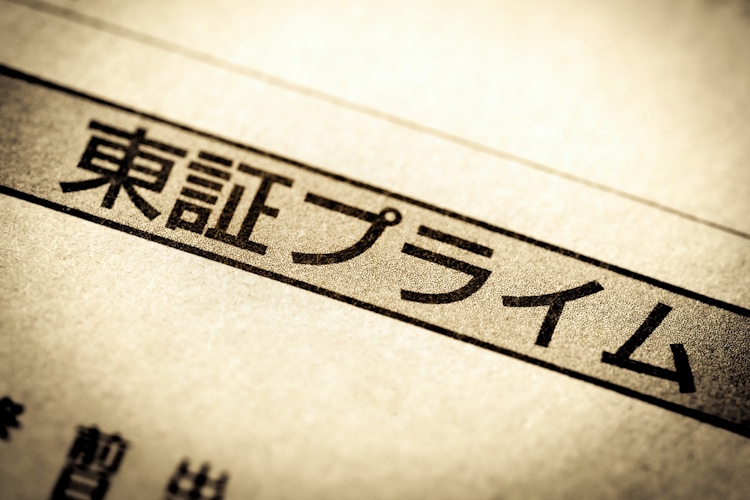2025年10月21日に高市内閣が発足し、物価高対策として冬季の電気・ガスへの負担軽減やおこめ券の配布(日本維新の会)などの案が出ています。しかし、スタンダードな物価高(インフレ)対策とは、日本銀行などの中央銀行が政策金利を上げることでインフレを抑制する政策のことを指します。
本記事ではインフレの種類と、スタンダードなインフレ対策を行った時のプラス面とマイナス面、個人の資産運用への影響について見ていきます。
- スタンダードな物価高対策とは、物価上昇に見合うよう中央銀行が利上げを行うこと
- スタンダードな物価高対策にはプラス面とマイナス面の両方がある
- 物価高対策は個人のローンや資産運用にも影響が大きく、利上げへのハードルは高い
インフレは2種類ある
インフレには、「ディマンド・プル型」と「コスト・プッシュ型」の2種類があります。
ディマンド・プル型は、消費者などの購買意欲が強く、生産者やサービス業者などの供給が追い付かないことで発生するインフレです。
コスト・プッシュ型は、消費者などの購買意欲が弱いにも関わらず、原材料費の上昇や人材不足による人件費の上昇などにより、生産やサービスのコストが上昇することで発生するインフレです。。
一般的には「ディマンド・プル型」は良いインフレ、「コスト・プッシュ型」は悪いインフレと言われています。
スタンダードな物価高対策のプラス面
スタンダードな物価高対策では、各国の中央銀行が物価の上昇や労働市場の状況を確認しながら物価上昇に見合うようなかたちで利上げし、物価の上昇を緩やかになるよう働きかけます。
金利を上げることにより、他国(主に米国)との金利差が縮まり、他国の通貨に対して自国通貨が高くなる傾向が強まります。それが輸入物価を下げる方向に働くというプラス面があります。
また、政策金利を上げることで預金金利も上がり、預金者にとってプラスの効果もあります。
スタンダードな物価高対策のマイナス面
スタンダードな物価高対策のマイナス面としては、個人では金利が上がることでお金を借りづらくなる、現在住宅ローンなどを変動金利で借りている場合などは今後の返済額が増えるなどがあります。
また、企業は借り入れと返済を繰り返しながら事業を行っているため、金利負担が増えると企業の収益を圧迫し、株価を押し下げる要因にもなります。
国も金利が上がることで、借り換え後の利払い費が増え、社会保障費(年金・医療・介護・子育て支援など)や地方交付税交付金などの予算組みに負の影響を与えます。
| プラス面 | マイナス面 |
|---|---|
| ・金利差の縮小により円高方向に動く傾向があり、輸入物価を下げに寄与。 ・預金金利の上昇により預金者の受け取る利子が増える。 |
・金利の上昇し借り手側の負担が増す。 ・借入の多い企業の業績への下押し要因になる。 ・国債の利払い費が増加する要因になる。 |
スタンダードな物価高対策の資産運用(投資)に対する影響
ここでは、スタンダードな物価高対策の資産運用(投資)に対する影響を、株式、債券、REIT(不動産投資信託)に分けて見ていきます。
株式
株式に関しては、金利上昇は銀行など資金の貸し手に対してはプラスに作用しますが、借り入れを行う企業にとってはマイナスに作用し、株価下落の要因の1つになります。
債券
債券に関しては、金利が上がることで、保有している債券の価格が下がるリスクがあります。
逆に新しく発行される債券や変動金利型の債券では、利上げ前の債券より利率が高くなる(利子が増える)プラス面もあります。
REIT(不動産投資信託)
REITに関しては、銀行からの借入金利が上昇することで収益が圧迫され、分配金の減少や、REIT価格が下落するリスクがあります。
また、REITが海外資産へ投資をしている場合は、円高になることで投資資産(円換算)が目減りするリスクが発生します。
まとめ
日本政府は、数兆円単位の物価高対策を検討していますが、スタンダードな物価高対策(中央銀行による政策金利の引き上げ)の実行には、直接的な費用はかかりません。
ただし、スタンダードな物価高対策のマイナス面で説明した通り、変動金利ローンへの影響と資産運用(投資)に対するマイナス面があります。
住宅ローンの変動金利の利用率の高さ(※)や、国が推進する「貯蓄から投資へ」のメイン施策であるNISA(少額投資非課税制度)の運用などへの影響を考えると、利上げ(スタンダードな物価高対策)による物価高対策のハードルはかなり高いかと思われます。
※住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者調査(2025年4月調査)」によると、「利用した住宅ローンの金利タイプ」は変動型が79%を占めました。