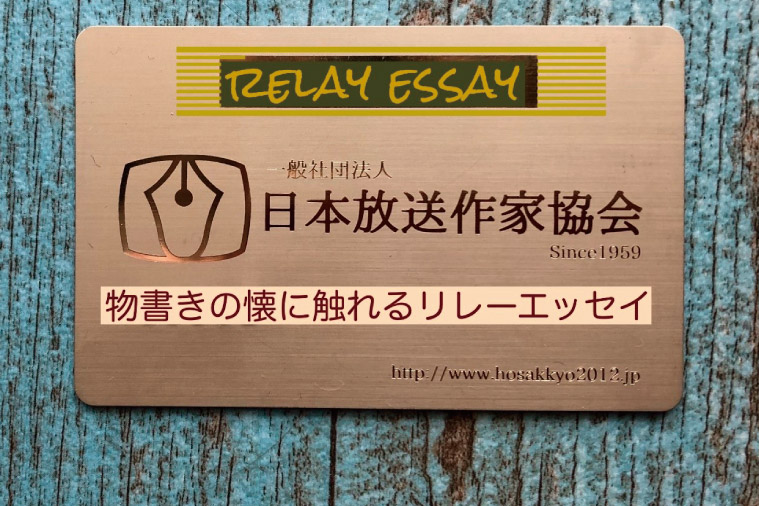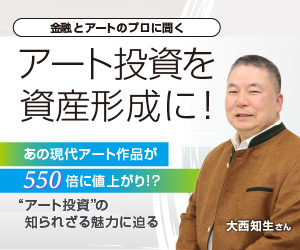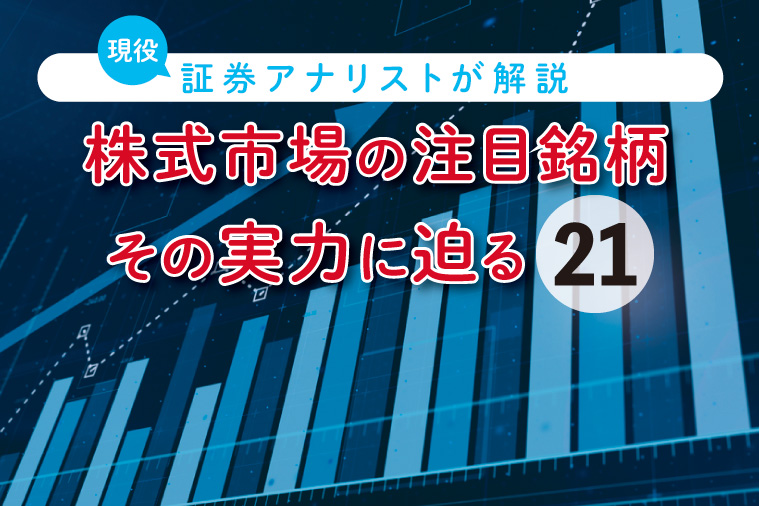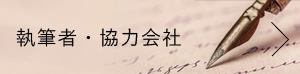テレビ、ラジオ、動画配信も含めて様々なコンテンツの台本や脚本を執筆する放送作家&脚本家が700人以上所属する日本放送作家協会がお送りする豪華リレーエッセイ。ヒット番組を担当する売れっ子作家から放送業界の裏を知り尽くす重鎮作家、目覚ましい活躍をみせる若手作家まで顔ぶれも多彩。この受難の時代に力強く生き抜く放送作家&脚本家たちのユニークかつリアルな処世術はきっと皆様の参考になるはず!
連載第109回は、放送作家協会で最年少の20代会員。マルチなジャンルに次々と活躍の場を広げている赤石真菜さん。
手紙交換に夢中だった小学生時代
 赤石真菜
赤石真菜脚本家
日本放送作家協会会員
昔から、手紙を書くことが好きだった。
小学生の頃は、近所の文房具屋で色々な種類のレターセットを購入し、友人に手紙を書いた。大量に集めたレターセットには、シンプルな無地のデザインから、お洒落なキャラクターものまでさまざまあり、「A子ちゃんにはこの色の組み合わせがピッタリで、B子ちゃんはこのキャラクターが好きだったから、限定デザインをあげよう……」といったふうに、相手の雰囲気に合った便箋と封筒をチョイスしていた。
当時、クラスの女子たちの間では「交換日記」や「プロフィール帳」が大流行していたが、その延長に王道の文通文化があったように思う。手紙の渡し方も人によってさまざまで、クラスメイトとは毎日顔を合わせるため手渡しで、近所に住む幼なじみはお互いの家の郵便受けに直接、投函し合った。小学校の高学年になると、隣町の塾に通う友人から郵送で届くようになり、地方在住のチャット仲間とは、いつでもインターネットで連絡が取れるにもかかわらず、自宅に手紙を送り合っていた。
今でこそ、スマホ一つで簡単にメッセージをやりとりできてしまう時代だが、文通にハマっていた当時の私は、自宅の郵便ポストを開けて、ハサミで封筒をカットする瞬間までワクワクしていた。手紙に書いてある内容は、なんてことのない、最近気になっているクラスの男子やテレビ番組の話題なのだが、“文通”という行為そのものに特別感やときめきを感じていたのだ。そのため、友人から貰った数々の手紙は全てファイリングし、今でもたまに読み返したりしている。
とはいえ、中学校に上がる頃にはガラケーでメールを送受信することが主流になり、手紙を書く機会といったら、友人への誕生日プレゼントに添えるバースデーカードくらいである。わざわざ手紙に想いをしたためて、それを相手と交換する機会などめっきり減ってしまった。
 小学生の頃から手紙を書くのが好きだった
小学生の頃から手紙を書くのが好きだった大人になって、92歳の祖母と文通を再開
ところが、昨年、10数年ぶりに文通を始める機会が訪れた。
その文通相手とは、高知県に住む母方の祖母である。92歳になり、長年住んだ市営住宅から老人ホームに移り住むことになった祖母は、新しい環境に馴染めずに塞ぎ込んでいた。そんな祖母に、「外からの楽しみが増えれば」と、東京在住の従姉妹が毎月ハガキを送るようになったことが始まりだ。このハガキを祖母はとても気に入り、東京に住む私や兄など、孫たちからの手紙を待ちわびるようになった。東京から高知までは気軽に行ける距離でもないため、このコミュニケーションが祖母にとってのささやかな楽しみになったそうだ。それ以来、私は祖母と定期的に文通を続けている。
しかし、日々の生活に忙殺されると、手紙の存在をすっかり忘れてしまうこともある。ある時、「もうすぐハガキを送るね」と祖母に伝えていたにもかかわらず、ポストに投函し忘れて何日か経ってしまったことがあった。すると後日、母づてに「おばあちゃんが真菜からの手紙をずっと待っている」という連絡が……。話を聞くと、施設の5階に住む祖母が、毎朝のように不自由な体で1階の郵便ポストまで覗きに行っていたと……。なんて申し訳ないことをしてしまった……としばらく引きずった私は、「思い立ったらすぐ手紙」と心に誓った。
それからというもの、なにかの節目に限らず、祖母にハガキを送るようになった。どこかに遊びに出掛けた際には、観光地のポストカードを購入して、「こんなところに行ってきたよ」と、海や山などの風景写真を添えて旅行の思い出を共有しながら、近況をつらつらと綴っている。
ただ、文通といっても、祖母から手紙で返事がくるわけではない。ハガキが施設に届くと、「お手紙、ありがとう」と祖母から電話がかかってきて、1枚のハガキにはおさまらなかったあれやこれやの会話を交わす。ハガキを送って祖母の声を聞くまでがセットで、2人の文通は成立するのだ。
昨年、母と高知に帰郷したときのこと。祖母が住む老人ホームを訪れると、部屋には私や兄夫婦、従姉妹から送られてきた大量のハガキが重ねて保管されていた。……保管する気持ち、わかる! 見える場所に置いて、いつでも読み返したくなるよね!と共感しながら、机の上に私が送ったばかりのポストカードが飾られているのを見て、「またすぐにハガキを送ろう」とうれしくなった。
 祖母への手紙では、旅行の思い出など近況をつらつらとつづっている。
祖母への手紙では、旅行の思い出など近況をつらつらとつづっている。“直筆”から伝わること
今の時代、他人の書く字を見ることが減ったように思う。作品の打ち合わせ中、ノートにメモを取る人と、パソコンに記録する人で分かれるが、後者である私は自分の字を見返す機会もなければ、他人が書いているメモを覗くことも少ない。
手紙は、そこに書かれた文章の意味だけに限らず、その人の“直筆”に触れる貴重な機会ではないだろうか。「あの人はどんな字を書くんだろう? きっと美しく繊細な字なんだろうな」と想像しても、案外その通りではなかったりして、予想ができず面白い。学生時代は、いかにも不良っぽいクラスメイトの男子がなかなかの達筆で、そのギャップにときめいたこともあった。
今回、改めて祖母にハガキを書いてみて、誰かに宛てて手紙をしたためることは、自分の字(の汚さ)や内面を見つめることでもあるのだなと思った。
次回は村上卓史さんへ、バトンタッチ!
放送作家の地位向上を目指し、昭和34年(1959)に創立された文化団体。初代会長は久保田万太郎、初代理事長は内村直也。毎年NHKと共催で新人コンクール「創作テレビドラマ大賞」「創作ラジオドラマ大賞」で未来を担う若手を発掘。作家養成スクール「市川森一・藤本義一記念 東京作家大学」、宮崎県美郷町主催の「西の正倉院 みさと文学賞」、国際会議「アジアドラマカンファレンス」、脚本の保存「日本脚本アーカイブズ」などさまざまな事業の運営を担う。