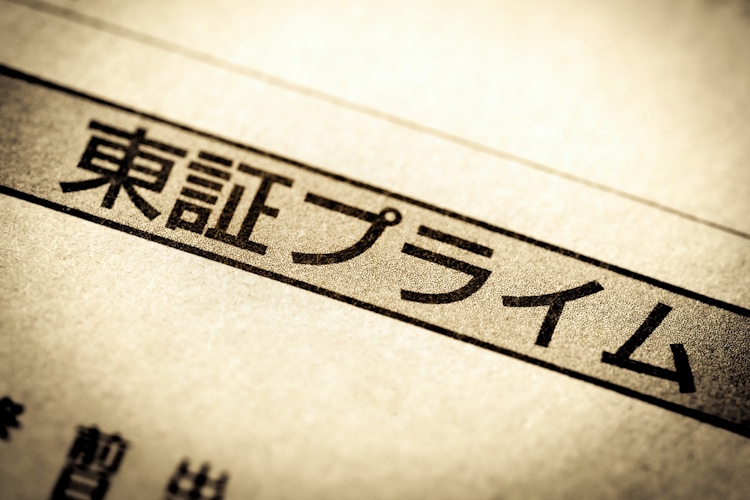宮崎県延岡市で保険業や資産運用のアドバイスに携わる小田初光さんが、地方で暮らす生活者のリアルな視点で、お金に関するさまざまな疑問に答えます。今回もNISAやiDeCoで資産形成を始めたいと思いながらも、何を買っていいかわからないと悩む30代の女性に向けて、投資信託を選ぶ際に知っておきたいインデックス運用とアクティブ運用の違いを、運用会社の情報発信という観点から見ていきます。
- 下値抵抗力の高さに注目して投資信託を選び、ゆとりを持った長期運用を心がけたい
- アクティブ運用の投資信託は高コストだが、ホームページでの情報発信が充実
- 直販投資信託のホームページには、投資初心者にとって学びとなる内容が満載
「下値抵抗力」を重視して、どっしり構える長期運用を
【質問】
NISAやりたいんですよ。iDeCoもやりたいんですよ。でもどうすればいいのかわからないんです。何を買えばいいのかわからんし、どこに行けば良いじゃろうか?
前回は、投資信託が長期にわたっていかに安定したパフォーマンスを得ているかに焦点を置くためにQUICKファンドスコアを参照し、特に重要な「下値抵抗力」に注目して話しました。
株式相場が大きな下落となった時、自身の投資信託が他の商品ほど下落しなかったら「ほっ」と心の中でつぶやき、「よっしゃ」と安心して、ほったらかしできる運用を実践できるかもしれませんが、現実としては相場の大きな下落によるダメージはひどく、心も折れてきます。
これを克服する材料として、自身の商品と比較する対象に、同じような商品とそうでない商品(アクティブ運用の商品を持っている場合は、前者は他社のアクティブ商品、後者はインデックス商品など)を選んで、比べて見てみると良いかもしれません。
下値抵抗力は、長期的パフォーマンスを見る際に重要な、リスクを軽減できる処方箋であることを実感して欲しいものです。
ここにきて日本の株式相場環境は、不透明さがいよいよ増してきていると言わざるを得ない状況になっています。関税の影響は株価に織り込み済みと言って楽観視する専門家も出てきているようですが、何を言っているのか?と思います。関税の影響と、これまでのお金ジャブジャブの金融緩和の影響は別問題です。これぐらいの影響で済むわけもありません。
もう一度言います。長期運用で大事な行動は、「心のゆとりと、どっしり構える」。永久に下落相場が続くわけがありません。あせらず下落相場を楽しむことです。
今の時代、何が一番リスクなのか? わかりきっています。何も行動を起こしていない、銀行の普通預金大好きな人です。

長期運用では「どっしり構える」ことが大切。下落相場だからといってあせって売ったりせず、冷静な判断が求められる
インデックス商品はコストが安くて安心だが……
今回は、インデックス商品とアクティブ商品を選ぶ際、これらの圧倒的な違いを共有できれば、商品を見極めるための1つのヒントになりますので話していきます。
6000近くある投資信託の中で、多くの金融専門家がNISAやiDeCoを活用するうえで推奨するのがインデックス商品になります。
確かにインデックス商品は、さまざまな指数に連動して運用することによって運用コストを安価にできるのと、わかりやすさは強みといえます。運用会社も大手が手掛けるものがほとんどで、販売チャネルの多さもあり、初心者投資家にも勧めやすくなっているのも特徴です。
逆にアクティブ運用の商品は、主にファンドマネージャーの采配で銘柄やポートフォリオ(資産の配分)も決められて、例えばグロース(成長)銘柄、バリュー(割安)銘柄などを基準とした方針で、投資家から集まったお金でポートフォリオを構築していきます。したがって、コストもそれなりに掛かります。
これだけだと、インデックス商品が大手だし安心と感じる初心者投資家が多そうですが、逆に初心者ほど金融知識を習得してほしいので、別の観点からアクティブ運用を実践してほしい。何よりも見てほしいのは、購入するに至るまでの窓口になる、運用会社のホームページです。
金融機関から購入するケースだと、購入商品のホームページも見たことがない人が大半でしょう。インデックス商品とアクティブ商品の違いの1つとして、ホームページのきめ細やかさに差があるのかなと感じています。
簡単に言えば、1つの商品についての説明や、報告書などが簡素化されているインデックス商品と、ファンドマネージャーが常に情報発信しながら投資家向けに伝えているアクティブ運用商品という違いです。
直販投資信託のホームページには工夫がある
アクティブ運用の商品のなかでも特に直販と言われている商品群は、ホームページにさまざまな工夫がなされています(第110回相談室参照)。残念ながら直販投信も、今では資産総額で苦戦を強いられることから、何かしら金融機関と提携しているところが増えているのは残念ですが、今も絶対直販だ! と言って運用しているファンドもあります。
これらのファンドのホームページに注目していきます。
直販投信は投資家が自ら調べて到達し、そして購入の意思を示さないと買えないファンドの宿命で、圧倒的に広告宣伝が少なく、商品があるという情報にもなかなかたどり着けません。ほとんどが口コミで、パフォーマンスを出して専門家や投資家にアピールしていくしかありません。
そんな中でホームページは投資家を呼び込むためのツールとして欠かせないものなので、情報公開も含めた窓口として、投資家が楽しめるようにしています。ここに注目していきたいと思います。
前号でもお伝えした直販投信で、①ひふみ投信、②結い2101、そして直販の先駆者である③さわかみファンドの3社のホームページを散策しながら理解していきます。
①ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)
レッド基調のホームページ。ひふみ投信などを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社は東京に本部を構え、現在はSBIグループ傘下で証券取引所に上場。5つの直販ファンドを手掛け、ひふみ投信はその中の1つになる。
年1回の報告会、毎月のセミナー、定期的な社会科見学、そしてセミナー動画など満載。
②結い2101(鎌倉投信)
グリーン基調のホームページ。運用会社は鎌倉に本部を構える。
年1回の報告会、毎月のセミナー、学ぶためのツール(結い日和)、そして動画、勉強会など満載。
③さわかみファンド(さわかみ投信)
ブルー基調のホームページ。運用会社は東京に本部を構える。
年1回の報告会、毎月のセミナー、全国開催の定期的な勉強会、そして定期的な企業見学会。読者参加型の「夢プロジェクト」など、動画も歴史がある分だけ充実。
学びツールにとどまらない直販投信ならではの「お宝」
言えることは、3社とも投資家が勉強できる環境が整っていることです。初心者投資家でもホームページにたどり着ければ、学びツールが満載です。
さらに今回うれしい情報として、さわかみファンドでは「ご縁を紡ぐプロジェクト」「長期投資家デビュープロジェクト」として、毎月動画コンテンツで投資知識を学びながら、最長3年間、毎月1000円分のファンドを付与してもらえる、自己負担なしで投資家になれるプロジェクトが開催されています。NISAを始めたい方、またはやっているが直販商品でもやってみたい方などにとっては夢のプロジェクトといえます。
このようにホームページにはお宝が詰まっています。まずは開けること、見ることから始めてみましょう。