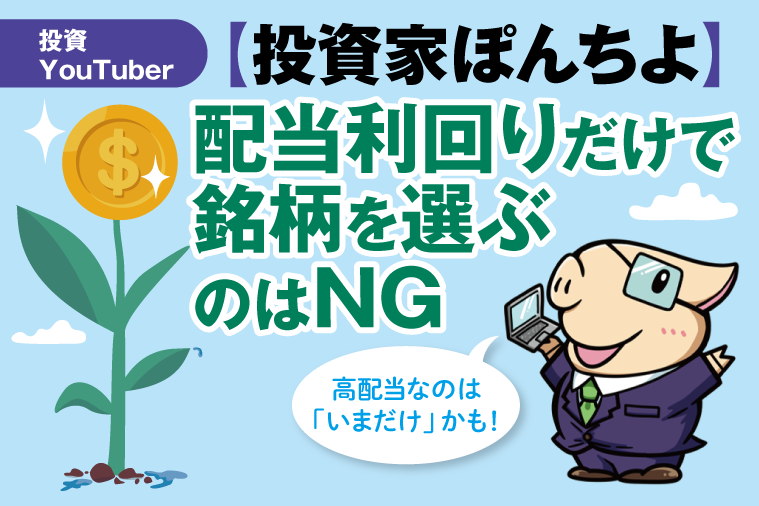宮崎県延岡市で保険業や資産運用のアドバイスに携わる小田初光さんが、地方で暮らす生活者のリアルな視点で、お金に関するさまざまな疑問に答えます。今回は、金融機関でNISAを勧められた相談者が、成長投資枠とつみたて投資枠の両方で投資信託を購入したことを受けて、投資初心者が2つの投資枠をどう活用すればよいかを考えていきます。
- NISAのつみたて投資枠はリスクを抑えて運用できる、投資初心者向けの投資枠
- スポット売買で失敗する投資家も多いが、経験によって安値で買う投資も可能になる
- 2つの投資枠を活用するには自己研鑽が大切。初心者は成長投資枠での積立投資から
つみたて投資枠は投資初心者のために設計されている
【質問】
新NISA制度はわかります。ただ、成長枠だの、つみたて投資枠だのと、いまいちわかりません。金融機関で聞いてもわけがわからず、両方入ったのですが問題ないですよね。簡単で良いので、成長枠とつみたて枠とどっちが良いのかを教えてください。
投資信託でNISAを始めた方は、「何枠」で商品を購入したのか? 大半の方が「NISA商品だから大丈夫。そんなこと知らんわ」との回答になるでしょう。確かにNISAを活用しているのは事実ですので、どちらも同じ投資と考えて遜色ないのですが、なぜ2つの枠があるのかを考えれば、それぞれの役割が見えてきます。
もう皆さんも内容などは聞いたことがあるので知っていると思いますが、今一度NISAの枠についておさらいさせていただきます。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間に運用できる 金額 |
240万円 | 120万円 |
| 投資する方法 | 制約なし | 積立投資しかできない |
| 投資できる商品 | 投資信託、ETF、 上場株式など |
投資信託、ETF |
| 商品数 (2025年7月14日時点) |
4601本 | 336本 |
2つの枠の大きな違いとして、年間に運用できる金額が「成長投資枠」が最大240万円、「つみたて投資枠」が年間最大120万円であることが挙げられます。両方合わせて保有できる生涯の非課税限度額は、1800万円が最高値です。
成長投資枠の商品には投資信託だけでなく上場株式も含まれますので、運用できる金額が多くなっています。一方のつみたて投資枠は商品が投資信託とETF(上場投資信託)のみ、その選定基準もノーロード(購入時手数料無料)が原則、信託報酬も一定水準以下とコストも低めであり、信託期間も無期限がほとんどで長く運用できるのが特徴です。
そして重要なのは、成長投資枠が制約なしなのに対して、つみたて投資枠は積み立てしかできない(自由に買い増しなどできない)という違いです。
成長投資枠とつみたて投資枠で、投資できるお金がなぜ違うのか? なぜ、つみたて投資枠では積立しかできないのか? このことから、つみたて投資枠は運用を始めたばかりの、初心者向けの枠であることがうかがえます。商品数にしても、2025年7月14日付で成長投資枠は4601本、つみたて投資枠336本と、つみたて投資枠は圧倒的に商品が少なく、選びやすくなっています。少額からの積立ができる商品が多い傾向です。
積立投資専門であるつみたて投資枠の大きなメリットとして考えられるのは、どの商品も一定のお金で定期的に購入して、一定の運用ができる積立投資によって投資のリスクを抑えられることです。聞いたことがあると思いますが、「ドルコスト平均法」のイメージがまさに実践できます。あとは景気の波を吸収できるよう、長期で積み立てを行うことさえできればオッケイ。このようなイメージで作られたのが「つみたて投資枠」とも言えます。
だったら相談者は初心者なのに、どうして金融機関で両方の枠を勧められたのか? それは定かではありませんが、2つの枠を両方勧めることは一概に間違いであるとも言えませんので、次の章で説明していきます。
投資家の運用パフォーマンスはなぜ低下するのか?
投資の世界に絶対はありません。世界で日常的に起こっているありとあらゆる事件もそうですし、それにより日々大きく動く世界の株価もそうです。企業も何の業種が上がり、何が下がるかなど、考えてもらちがあきません。そもそも、明日の株価がどうなるかを必ずしも当てる必要もありません。それが刻一刻と動き続ける経済に投資するということです。
ただ言えるのは、世界経済全体の成長は止まることはないという事実です。人間が生きる限り、経済成長は続きます。株価もそうです。黙ってその流れに乗ればいいだけです。市場に居続けるだけで結果は付いてきて、居続けないとパフォーマンスは大きく悪化します。
これこそまさに長期運用の極意なのですが、運用パフォーマンスが低下する原因は、多くの投資家はスポット売買の頻度が高く、結果として高値で買い、安値で売っていることです。これがNISA制度の成長投資枠の大きなリスクであり、初心者が陥りやすいリスクでもあります。
このリスクを逆に言うなら、「高値で買い、安値で売る」を、「安値で買い、高値で売る」に近づけることができるならば、成長投資枠での投資も「あり」となります。これは経験と、身近に相談できる方があれば可能になると思います。
「安値で買い、高値で売る」投資を目指すには
例えば、①金融セミナーなどで専門家の生の声を拾う、②セミナーの参加者同士で状況を共有する、などができます。初心者は自分自身で行動を起こすことにより、知識を習得できます。できれば定期的なセミナー、勉強会への参加がベストですね。
相談者の質問に戻りますが、そこから言うとNISAの両方の投資枠での購入もありと言えます。ただし、自己研鑽が絶対に必要ということを忘れなければ、と付け加えておきます。
最近のデータで、アクティブ運用の定期定額購入(積み立て)比率が高い投資信託は、投資信託の成績よりも、投資家の平均損益が上回ったという報告があがっているそうです。これは心理学的にも、つみたて論者は「ほったらかし」ができ、売買頻度も少なく、結果的に上手い売買ができている結果がリターンにつながっているのでしょう。アクティブ運用商品の多くは、つみたて投資枠の対象外です。
最後になりますが、「成長投資枠」「つみたて投資枠」の違いを、そのままパフォーマンスの差として出すことは難しいです。「どちらを中心でやる方が良いか?」より、初心者がNISAで投資を始めるなら、株式を中心としたコストが安価な投資信託で、成長投資枠を使って定期定額購入の積立投資をしながら、安くなったら買い、必要なら高値で売り、長く持ち続けるが、正解ではないでしょうか。できれば、積立投資で買われている比率の高い商品がなおさら良い、と付け加えておきます。