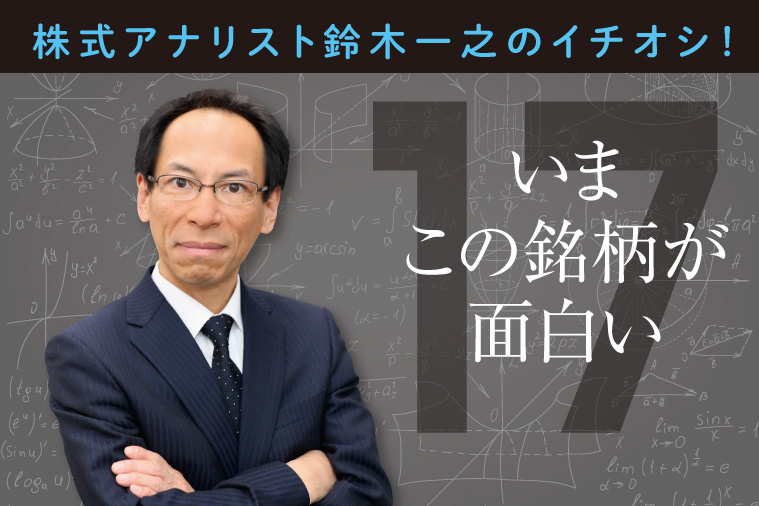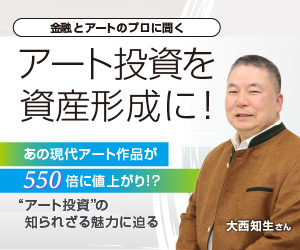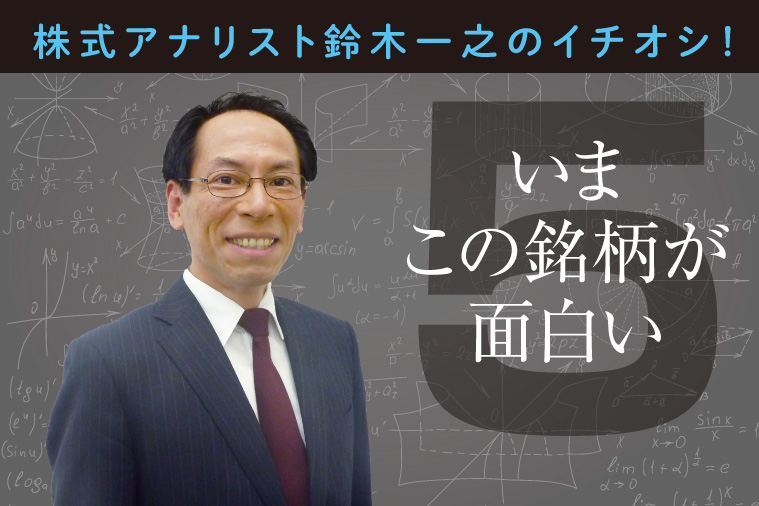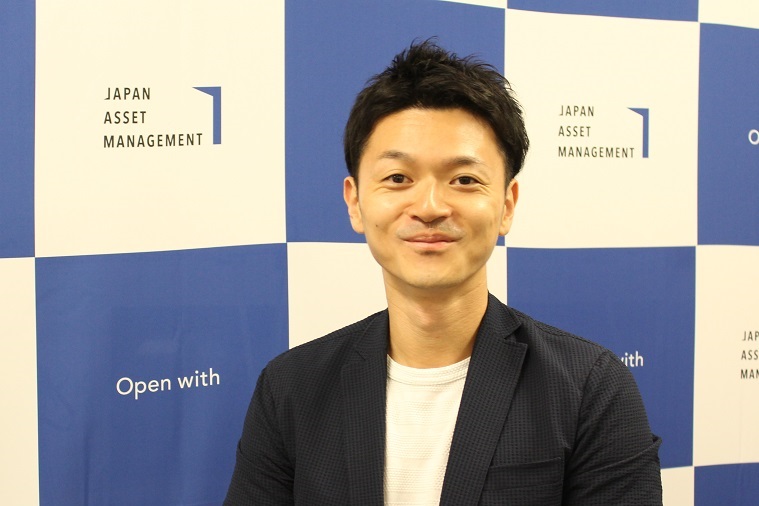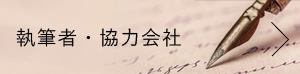1億度超の超高温と、磁力線による磁場
反発しあう原子核を強引に近づけて融合させるには、ひとつには、自由に飛び交う原子核のスピードをどんどん引き上げればよいと考えられます。原子レベルでスピードを上げるには、プラズマの温度を高くすることが求められます。
太陽の中心は1600万度まで達しており、地上でも1000万度くらいになってようやく核融合反応が起こります。しかし地上の核融合炉では、空気の10万分の1程度の非常に希薄な水素プラズマを用いることになるので、太陽よりもずっと高い温度で核融合を起こさなければなりません。そのために太陽の1600万度をさらにもう1ケタ超える、1億度以上の超温度が必要となります。
日本が開発した核融合のための実験炉「JT-60U」では、1996年に5.2億度という世界最高記録を達成しました。この記録はギネスブックに認定されています。
1億度という想像を絶する高温で、希薄なプラズマ状態にした水素を安定的に保持しなければなりません。太陽は自分の重力で水素を引き留めていますが、しかし地上ではそこまで強力な重力は使えません。
そこでどうするかというと、磁力線による磁場を使って水素のプラズマを封じ込めます。強力な磁石を使って作り出した強力な磁力線を使って、ねじれた状態のドーナツ型の円環(トーラス)を日本は編み出しました。電流のまわりには円周状の磁場(磁力線)ができることを利用して、電流をうまく制御すればねじれ状態のトーラスでプラズマを封じ込めることができます。このねじり方がユニークでさまざまな工夫が凝らされています。
電気抵抗ゼロの「超伝導現象」
プラズマを閉じ込める磁石には、銅コイルではなく超伝導コイルが用いられます。水銀をマイナス269度の絶対零度まで冷却すると、電気抵抗がいきなりゼロになるという超伝導現象は、1911年にオランダのカーメルリング・オンネスによって発見されました。オンネスはこの功績によって1913年にノーベル物理学賞を受賞しています。
1980年代にはマイナス196度でも超伝導現象が起こる、高温超伝導材も発見されました。今では医療用MRIやリニア新幹線の分野で実用化されています。プラズマを封じ込めるための磁石に通常の電磁石コイルを用いると、求められる磁力があまりに強力であることから、核融合炉で作り出した電気のほとんどが磁力コイルで消費されてしまいます。これではなんのための核融合炉なのかわかりません。
そこで電気抵抗がゼロでそれだけ効率のよい高温超伝導による強力な磁力が用いられることになったのです。
プラズマの内部で重水素と三重水素が核融合反応を起こすと、アルファ粒子と中性子が発生します。核融合エネルギーの8割はプラズマ内部にとどまることなく、電荷を持たない中性子として外に飛び出してきます。それを「ブランケット」という外壁で受け止めて、発電に必要な熱を取り出します。
ブランケットは鉄と水とリチウムできていて、プラズマを覆う真空容器の内側の壁一面に張り巡らされています。中性子は透過しやすいので、それを受け止めるブランケットは60センチほどの厚みが必要です。ブランケットによって中性子をとらえ、中性子のエネルギーを熱源に変換します。
厚みのあるブランケットに中性子が何度も衝突して、熱エネルギーが蓄積してゆきます。それを冷却水(といっても300~450度もの高温)、または700度のヘリウムガスとして取り出して、核融合炉の外に運び出して蒸気を起こしタービンを回して発電に利用します。ブランケットで吸収されなかった中性子も、そこから外には漏れないようにブランケットの外の遮蔽壁で吸収される仕組みになっています。
国際共同プロジェクト「ITER(イーター)」
究極のエネルギー源としての核融合炉の実用化計画は1950年代から始まりました。課題はたくさんありますが人類初の核融合炉を実現すべく、日本・米国・欧州・ロシア・中国・インド・韓国が共同で超大型国際プロジェクト「ITER(イーター)」を運営しています。
ITERは国際協力としては前例のない形式を採っています。1985年のジュネーブにおけるレーガン大統領とゴルバチョフ書記長による米ソ首脳会談がきっかけとして生まれました。2025年の運転開始を目指しています。
米国と中国が覇権を賭けて争う現代社会では考えにくいことですが、国際社会がひとつになって人類共通の大きな課題にチャレンジする、数少ない事例としてもITERの存在価値は大きいと思います。
目下のところ、ITERが直面する技術的な壁がいくつかあります。代表的なものが、1億度の高温を長い時間にわたって維持できるかどうか、です。
この壁をクリアしたとしても、すぐには燃料となる三重水素を入れることはせずに、しばらく核融合は起こさせずに実証実験を繰り返します。核融合に必要なプラズマの燃焼を長時間にわたって維持し発電を続けるために必要な、三重水素の増殖が理論通りにできるブランケット、それらを構成する新素材、および周辺機器の開発が必要です。
現在のスケジュールでは、2035年ごろにようやく三重水素と重水素による核融合反応を確認するというプランになっています。2035年にプラズマの燃焼実験にとりかかり、そこから実際に運転する原型炉の建設に進み、2040年代になって実際の発電試験をする計画です。核融合を用いた発電所として自立するには、そこからさらに実証実験を繰り返す必要があり、核融合発電所の初号機が正式にスタートするのは2050年代半ばくらいとイメージしておいた方がよさそうです。
放射性廃棄物が少なく、事故が起こりにくい特徴
核融合炉には燃料が無尽蔵という特徴だけでなく、原発と比較して放射能が外部に流出するような事故が起きにくい、という安全面に最大の特徴があります。
プラズマとなっている水素の原子核という燃料は、燃焼時間が数秒しかもたないため、常に外部から燃料を入射し続ける必要があります。燃料の供給が止まれば、核融合炉の燃焼は数秒で止まります。したがって、原発のように冷却を必要とするような核燃料棒の操作は必要なく、熱暴走による大事故は起こらず発電所全体が壊れるような事故にはなりにくいと見られます。
また、燃料を入れ過ぎたとしても、プラズマを制御することができなくなって、やはり核融合炉は停止します。プラズマに不純物が混入しても1億度の高温が維持できず、プラズマが冷えてやはり核融合は止まります。
廃炉を考えた場合、核融合炉から出る放射性廃棄物は高レベル廃棄物に分類されるものがないので、原発と比べて毒性指数は1000分の1程度にとどまります。さらに燃料に関しても、運用中に必要なものは重水素とリチウム、初期装填用の三重水素に限られるので、燃料サイクルから見ても発電設備の敷地内で閉じてしまうことが可能です。
21世紀の後半には、私たちが日常的に使う電力と水素の製造のかなりの部分を核融合が担うという未来が想い描くことができます。関連企業としては、三菱重工業(7011)、東芝(6502)、三菱電機(6503)、日本製鉄(5401)、キヤノン(7751)、古河電工(5801)が挙げられます。
温暖化ガスの排出を限りなくゼロに抑えて、安定したエネルギーを供給できる核融合に関する技術は、地球全体の未来に向けて大きな役割と可能性が期待されます。