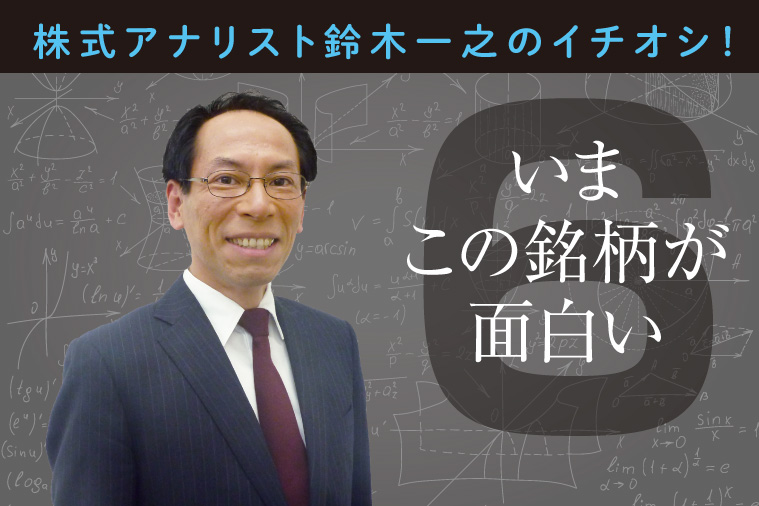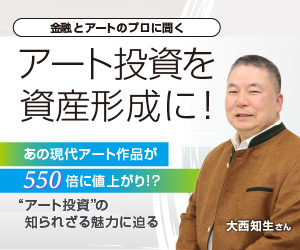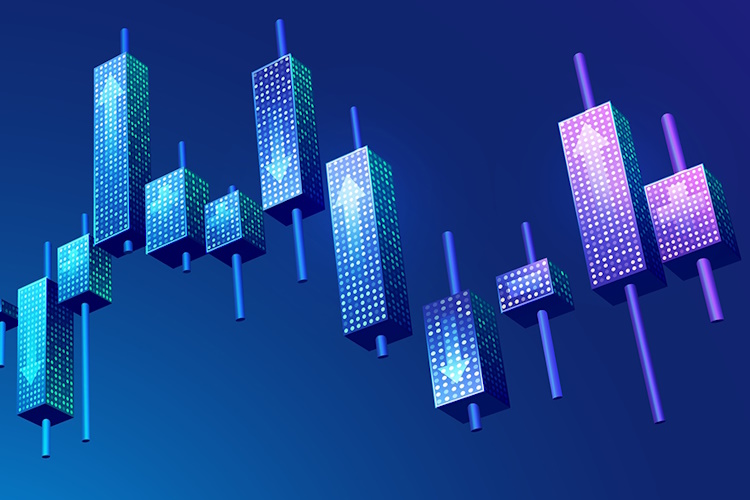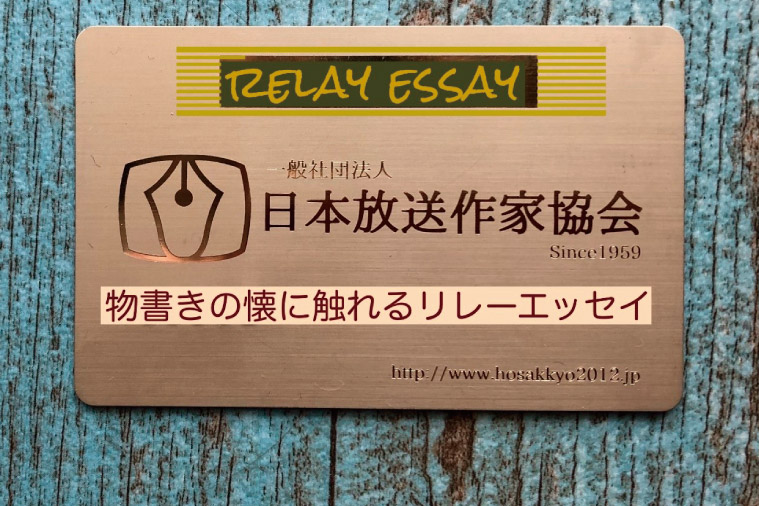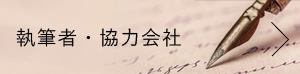「商社・冬の時代」を経て、2000年前後から経営環境が一変
1970年代後半から80年代前半にかけて、「商社・冬の時代」と呼ばれた時期がありました。もはや重厚長大産業の時代ではない、というのがその当時の支配的なムードでした。1970年代のロッキード事件(丸紅)、ダグラス・グラマン事件(日商岩井)、90年代の銅地金不正取引事件(住友商事)など、社会的な不祥事が相次いだことも影を落としました。
その後に訪れたバブル経済期に一時は業容も拡大しましたが、バブルが崩壊した90年代には再び「商社不要論」が盛んに持ち出されました。IT革命が進展すれば仲介業者としての商社は不要になるという説です。
その厳しい経営環境が2000年前後から一変していったのです。不良資産の償却を進めると同時にリスク管理手法を徹底させたこと、経営の「選択と集中」によって高収益部門が育ったこと、中でも集中させた資源・エネルギー部門が資源価格の高騰によって稼ぎ頭に成長したこと、がその理由です。
伝統的な観点から述べれば、総合商社の商社たる機能は、オーガナイザー機能、事業投資機能、企業間信用、情報収集機能の4つによってもたらされています。収益もここからあがり、中でも開発案件の豊富な高度成長期には、産業界を横断する形でのオーガナイザー機能が力を発揮しました。
その上で、2020年以降の商社ビジネスは、事業投資会社としての機能が再び注目されてくるようになるでしょう。総合商社が新規に事業投資を行う場合、本体の既存事業を分社化・子会社化する、新規の子会社を立ち上げる、既存の事業に資本参加する、の3つのケースがあります。規模が大きければM&Aに発展する場合もあります。
デジタル革命の大半で総合商社の事業投資ビジネスが関わる
バフェット氏は年に一度の「株主への手紙」を除けば、自社の投資案件に関してほとんどその真意を語りません。しかし今回の商社株への投資では、従来の慣行を破って声明を発表しています。
日本の大手商社が将来にわたり「世界中で合弁会社をつくりパートナーシップを拡大する可能性が高い」との前提に立った上で、「将来にわたってお互いに利益をもたらす機会があると望んでいる」ということです。自身が率いる投資会社であるバークシャーと日本の総合商社との協業を望んでいるようです。その上で最終的には9%を超えるまで保有比率を引き上げる可能性があります。
現在のコロナ危機に際して、お気に入りだった航空会社株をすべて売却したばかりです。一方では金鉱株を新たに買い入れて、これも世界を驚かせました。それに続く今回の日本の総合商社株への投資です。
現在、世界中の人々の目の前で始まっているデジタル革命の大波が社会の在り方を大きく変えつつあります。モビリティ、医療、食品、生活資材、小売の現場、電力・ガスの社会インフラ、都市開発など、社会のすべての分野でデータエコノミーによる大きな変革が始まっています。
物流、地球環境、エネルギー、あらゆる産業分野が一斉に、かつ猛烈なスピードで変わりつつあります。その大半の分野で総合商社の事業投資ビジネスが関わってきます。そのような変革をミクロベースに小分けして個々にとらえてゆくよりも、総合商社さえ押さえてしまえば、社会の巨大な変革を丸ごとトータルで、パッケージとして手中に収めることができます。
そんなことができる企業群は世界をつぶさに見渡しても日本の総合商社の他には見当たらないのではないでしょうか。ひょっとしたらバフェット氏の着眼点はそのあたりにあるのかと考えられます。
産業革命に例えられる現在のデジタル化の大波を、19世紀の産業革命期に生まれ育った総合商社の未来像に重ねるのもひとつのアプローチです。株価は目下のところホットな状態にありますが、少し熱気が冷めたところであらためて総合商社株への投資の検討をしてみる価値は十分にありそうです。