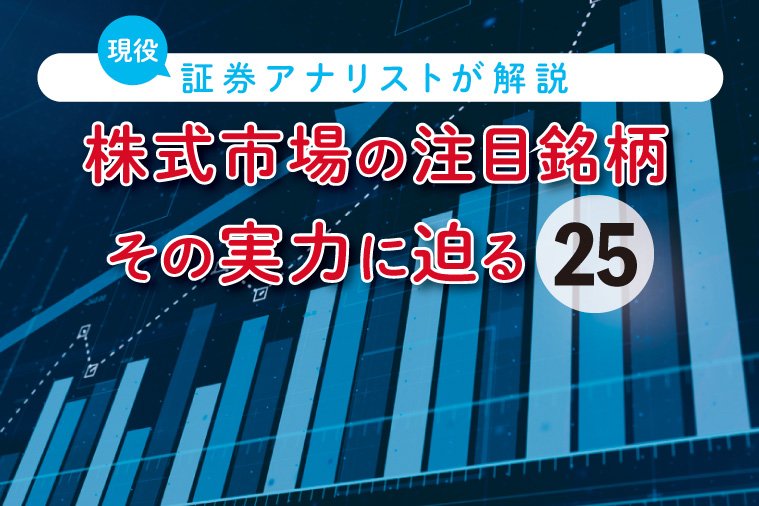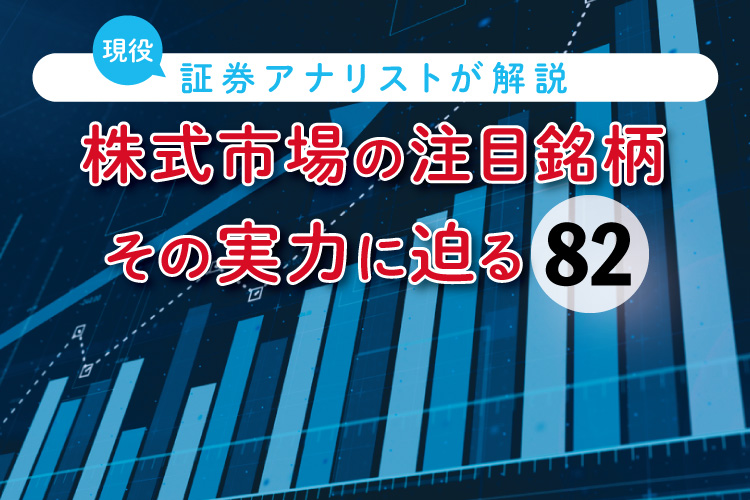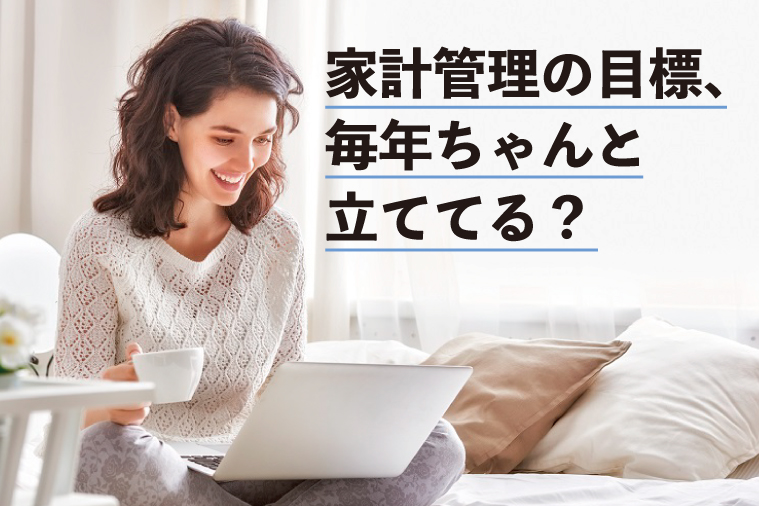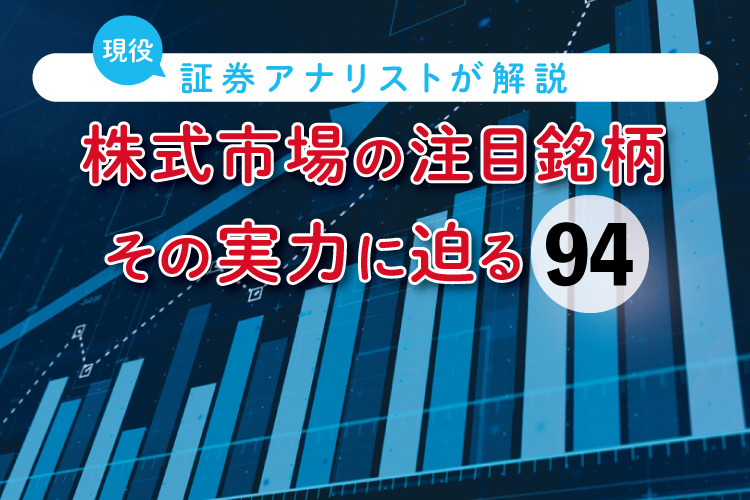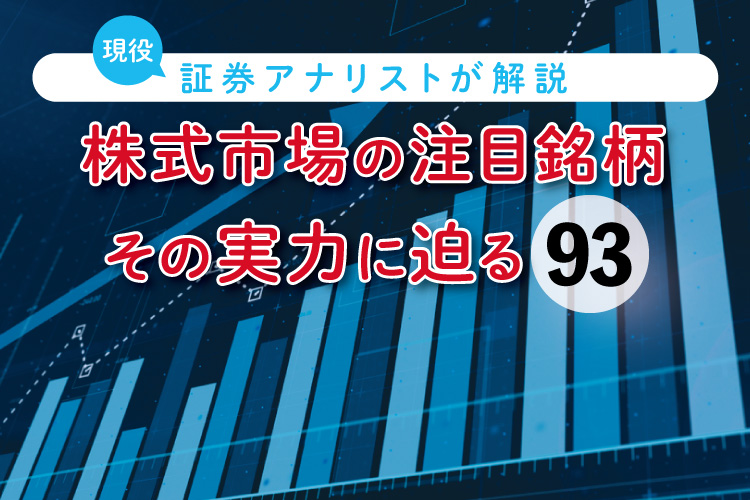宮崎県延岡市で保険業や資産運用のアドバイスに携わる小田初光さんが、地方で暮らす生活者のリアルな視点で、お金に関するさまざまな疑問に答えます。今回も前回に引き続き、新興国への投資を勧められたという相談者へのアドバイス。小田さん自身の経験と、過去20年あまりの投資信託の成績に基づいて、新興国投資について考えていきます。
- 「オルカン」の9割が先進国、7割が米国。リスクを考えて一部換金も検討
- 20年前の新興国投資の経験では、ベトナムの投資信託は長期で成果が出た
- 過去20年で新興国投資の成果は先進国と同等かそれ以下。成長力への過信は禁物
米国株式が大部分の「オルカン」にはリスクも
【質問】
これからはベトナム、インド、中国など新興国にNISAで投資するのも良いですよ~と、主に新興国市場の株式で運用する投資信託を証券会社で勧められました。確かに、今でも全世界株式(オルカン)をやっているので良いかもねと思い、考え中です。発展途上国への投資をどう思いますか? アドバイスください。
前回までは新興国と先進国のGDPと一人当たりのGDPを比較しながら、新興国市場の現状を考えていきました。
これらの比較が、投資信託などの商品を運用するにあたって全てではありませんが、国全体が豊かになるのと、人それぞれが豊かになっているかどうかは、かなりの乖離があるのがわかったと思います。
特に一人当たりのGDPでは、2024年時点で中国はロシアよりも下位にある現状にビックリします。新興国は、まだまだ豊かさとは程遠いことがわかります。
銀行や証券会社などから、新興国と言われる地域(中国、インド、ベトナムなど)の投資信託を勧められたという話を多く聞くのは、GDPの比較が根拠になっているのかは定かではありませんが、あながちもそうかもしれません。一人当たりGDPが低いということは、新興国は日本を含めた先進国よりは、まだまだ成長が望めると考えてもおかしくありません。
相談者が運用する投資信託の世界株式(オールカントリー)は、投資先の90%を先進国(米国が70%弱)で占めており、新興国はわずか10%という構成です。米国中心での運用はそれなりにリスクを抱えていますので、4年余りで倍近く利益が出ている現状でしたら、積立は維持しながら、一部換金(解約)されても良いかもですよとアドバイスさせていただきました。
今は世界のインフレや株高の中で米国一人勝ち状態が続いていますが、政治と紛争がどうなるかによって、先は見えなくなりつつあります。世界株式でも新興国に投資をしていることには変わり有りませんが、なんせ10%だけです。ここからしても、新興国と言われる地域に投資する商品を買って、「オルカン」のリスクをヘッジするという意味はあると思います。
20年前に始めた新興国投資の結果
ここからは私の経験談です。約20年前から新興国に投資して、どうなったのか? 失敗から学んだことなどを話していきます。
中国株の個別銘柄と投資信託を運用
20数年も前から「新興国の成長はまだまだ、これからだ~」と、マネー雑誌などで新興国ブームが騒がれていました。このマネー雑誌などで私も引っかかった(笑)のかもしれませんが、新興国投資のスタートは中国の株式取引でした。
当時の中国の成長は凄まじいものがあり、2000年代前半はGDP世界4位、年10%以上の経済成長は当たり前で、人口増も続いており、「先進国に追いつけ追い越せ」を前面に出す政策を打ち出していました。

2000年代前半から中頃にかけて、中国の経済成長率は突出していた
私は2002年から中国の大手国有銀行、鉄鋼銘柄などの個別銘柄を買い、2~3年程度の取引で運よく利益を得ることができました。それが今ではどうなったのか?
今では、一部は残っているものの、ほとんどを売っています。中国の投資信託の運用を開始したのは2005年でしたが、これも短期運用で、約3年で換金して今はありません。
当時売ってしまった理由は、「イケイケどんどん」の国の政策が好きになれなかったことがあります。
インドへの投資は、当時は私の勉強不足もあり行っていませんでした。
ベトナム株式と投資信託、そして投資事業匿名組合
次はベトナム株式と投資信託への投資です。2006年当時のベトナムのGDPは世界58位、インドがすでに14位※ですから、成長性をにおわせていた国の一つでした。
ベトナムの通貨はドン。まだまだ通貨が安かったことから、株式投資と米ドル建ての外国投資信託、そして同時に期間3年のベトナムファンド投資事業匿名組合と、中国(マカオ)投資事業匿名組合にチャレンジしています。
結果ですが、株式投資はあまり益はでませんでしたが、ベトナムの投資信託は未だ継続中で、約2.5倍と益が出ています。
投資事業匿名組合に関しては、どちらも益はなく、分配金も一度も出ずに、資産を大きく減らす結果となっています。ここにある投資事業匿名組合とは、出資者が匿名で資金を提供し、出資を受けた営業者がその資金を使って事業を行う契約形態のことです。匿名組合にはメリットとデメリットが存在しますが、最大のデメリットに元本割れ、流動性の低さ(解約しにくい)、そして営業者のコントロール(信用性)があります。特に予定したお金が集まらなかったなどの理由で出資総額が少ないものが多く、少額なほどなおさらデメリットが強まっていく傾向にあります。
短期売買は失敗もあったが、長期運用は成功といえる結果に
結論としては、20数年前から新興国に投資していましたが、短期売買(ベトナム株式や投資事業匿名組合)は失敗しながらも、長期運用(ベトナム投資信託など)は成功していると言ってもいい結果となりました。いかに長期運用が重要かを感じることとなりました。
この20年で新興国の投資信託は成長したのか?
ここで比較したいのは、同じ時期に長期で運用していた新興国以外の投資信託が、この20~25年でどうなったのかです。
当時あれだけ「まだまだ成長するよ」と言われた新興国投資、私が投資していた先進国(日本)投資と比較すると、
- 中国株式
損保ジャパン拡大中国株投信(SOMPOアセットマネジメント)
分配金再投資基準価額 約3.8倍
2005年(設定時)10,000円 → 直近 約38,000円
(分配金受け取りの場合は約2.5倍) - ベトナム株式
FCグローバルベトナムファンド(米ドル建て、外国籍)
基準価額 約1.9倍
2007年 1,116米ドル → 直近 約2,130米ドル - 日本株式
さわかみファンド(さわかみ投信)
基準価額 約3.8倍(これまで無分配)
1999年(設定時)10,000円 → 直近 約38,000円
日本はと言うと、長期投資の王道であるさわかみファンドが1999~2025年で約3.8倍。中国は2005~2025年で分配金再投資基準価額が3.8倍となっていますが、分配金再投資コースでは分配金(普通分配金)は税金控除後に再投資され、実際の伸びは3.8倍をやや下回ることになります(2014年以降は、NISA口座であれば非課税で分配金再投資ができます)。ベトナムは、日本と中国を大きく下回ることになりました。そして過去20年間で、米国株式市場は5倍近く成長しています。
20数年前からあれだけ新興国の経済成長を言っていながら、パフォーマンスは日本とせいぜい同じかそれ以下で、米国には置いていかれています。
さらに新興国投資信託の純資産総額に至っては、このところは増えるどころか減少傾向にあります。これも大きなリスクだと思います。
新興国への投資は慎重に検討すべき
結論として、金融関係者の「これからは新興国の時代」は幻想であるということです。今でも新興国投資は魅力を感じるかもしれませんし、実際にIMFによる一人当たり名目GDPは新興国は下位の方を走っているため(2024年の予測値は米国6位、日本39位、中国73位、ベトナム123位、インド142位)※、成長余力はあります。
ただ、最近ではインド通貨のルピーが対米ドル最安値を更新したなど、景気減速への懸念が強まっています。また、格付投資情報センター(R&I)はカントリーリスク調査で、インド、中国、韓国の評価を下げています。すべて政情不安が原因なので、投資する際は慎重に検討するべきです。
もう一度言います。新興国が「まだまだ成長する」は幻想です。でも、長期で成長はしていきます。