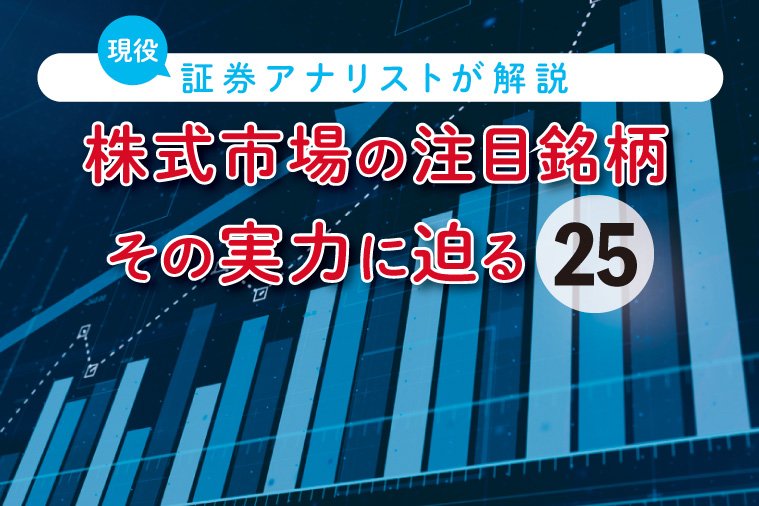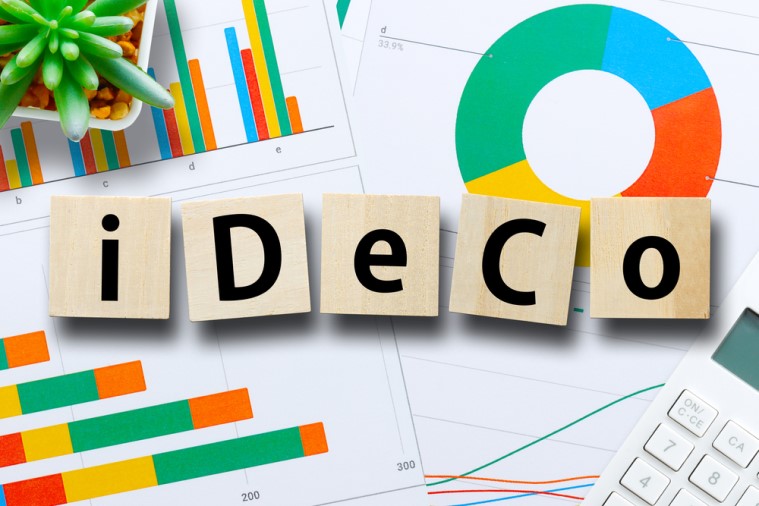資産運用を始める前にぜひ知っておきたいポイントをわかりやすく紹介する本連載。第5回は、「投資信託」を取り上げます。
はじめに~少額で分散投資ができる「投資信託」
今回は、「投資信託でできること」をテーマに投資信託の基本的な仕組みを見ていきます。
投資信託は運用を投資の専門家に任せられ、少額で分散投資ができる投資商品です。
投資の専門家が運用を行う
投資信託は、多数の投資家の方から集めた運用資金を、投資の専門家(ファンドマネージャー)が運用する商品です。
投資資金を集めるためには、その投資信託の内容を説明する書類が必要です。その書類のことを目論見書(もくろみしょ)といいます。目論見書にはその投資信託がどのような方針で運用されるのか、株、債券、リートなど投資対象はどれか、日本、米国、インドなど国別、先進国、新興国など、どの地域を投資対象にするかなどが記載されています。
ファンドマネージャーは、その運用方針に基づいて日々の運用を行います。
投資信託を購入した方は、ファンドマネージャーに運用を一任しますので、運用方法などについて意見をいうことはできません。購入した方は、基準価格の値動きや分配金の増減などを確認して買い増しや保有継続、売却の判断をすることになります。
目論見書の記載例
| 商品分類 | 属性区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位型・ 追加型 |
投資対象 地域 |
投資対象資産 (収益の源泉) |
投資対象商品 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ |
| 追加 | 海外 | 株式 | その他資産 (投資信託証券(株式)) |
年12回 (毎月) |
グローバル (日本を除く) |
ファミリー ファンド |
なし |
少額から投資が可能
投資信託は個別株に比べ少額から投資が可能です。
個別株投資の場合は、100株単位の取引になります。例えば株価1000円の会社の株式を購入する場合は、10万円(1,000円×100株)に加え手数料がかかります。投資信託のように複数の銘柄に投資するとなると、多額の投資資金が必要です。
投資信託は、金融機関により1回の最低購入金額が異なります。中には最低購入金額が100円からという金融機関もあります。100円は極端ですが、仮に最低購入金額が1万円としても、個別株投資に比べかなり少額から投資をスタートすることができます。
分散投資でリスクを軽減
投資信託は、分散投資を行うことで価格変動リスクや信用リスクなどの軽減を図ります。主な分散方法は「銘柄分散」と「地域分散」です。
銘柄分散はすべての投資信託で行われています。銘柄分散は景気や金利、為替の動きなどに対して異なる値動きをする複数の銘柄(会社)組み合わせることで、安定した運用を目指すために行われます。大きな値上がりを期待できない反面、大きな値下がりを防ぐことが期待できます。
地域分散は、世界の株や債券などを投資対象にしている投資信託で行われます。
それぞれの地域により好不況の景気サイクルが異なることに着目し、投資する地域を分散することで、基準価格の大きな変動を抑えることが目的です。
積立方式で投資信託を購入した場合
つみたてNISAなどを使って投資信託を購入する場合は、上記の銘柄分散、地域分散以外に時間分散の効果を得ることができます。
時間分散は、購入するタイミングを分けることで高値掴みを避け、平均の購入単価を下げることを目的とした投資方法です。この投資方法のポイントは、1回の投資金額と購入のタイミング(毎月同日など)を一定にするドル・コスト平均法を活用できる点です。また、長期投資につながりやすいのもメリットの1つです。
長期投資を行う目的も、価格変動リスクを抑えることにあります。株価はバブルの崩壊などにより短期的に大きく下落することがありますが、長期的には各国や世界のGDP(国内総生産)の成長などにより上下しながらも右肩上がりになる傾向があります。
最後に~投資信託は、長期的に資産を増やすことが目的の商品
今回は、「投資信託にできること」として、主に少額投資と分散効果について見てきました。投資信託は一般的に、分散効果を生かしながら10年20年と長期的に資産を増やすことを目的にした投資商品です。従って、積立投資についても触れました。
次回は、投資信託の「基準価額と分配金」について、「株価と配当」と比較しながら見ていきます。
知っておきたい資産運用のキホン【第6回】「分配金? 基準価額? 投資信託に関する用語を知ろう」はこちらから