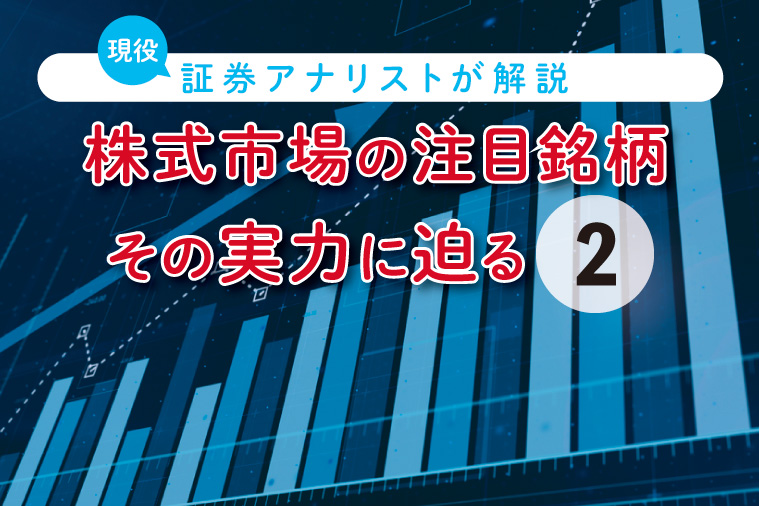日本は公的医療保険がしっかりしているため、医療費の負担はある程度抑えられています。しかし、紹介状なしでいきなり大きな病院を受診したり、ジェネリック医薬品があるにもかかわらず、もととなった新薬を選んだりすると、追加で費用負担が必要になることもあるのをご存知でしょうか。
- 保険適用でない医療サービスを受けた場合に発生する選定療養費
- 紹介状なしで大病院を受診すると、選定療養費が発生する
- ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望した場合にも選定療養費がかかる
選定療養費には複数の種類がある
選定療養費とは、病院などを受診することになった患者さん自身の選択で保険適用とはならない医療サービスなどを受けた場合に発生する費用です。
選定療養とされるものにはいくつかの種類があり、以下のものが代表的な例です。
- 入院時に個室や少人数部屋を選んだ場合にかかる差額ベッド代
- 大病院の初診料・再診料
- 時間外診療費
- 180日以上の入院費
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(新薬)の処方 など
今回はこの中でも、知らず知らずのうちに発生する可能性がある「大病院の初診料・再診料」と、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品処方」について見ていきましょう。
紹介状なしの大病院での受診、特別料金が追加?
健康に関する心配事が発生した場合、すぐに大きな病院で見てもらって安心したくなるかもしれません。
しかし、紹介状なしに大きな病院を受診すると、初診・再診いずれの場合も特別料金が追加でかかります。
一定規模以上の医療機関は紹介状なしで受診した患者さんから一定額の特別料金を徴収するよう、法律で義務付けられています。
選定療養費の徴収を義務付けられているのは、高度な医療技術を用いた治療を行う「特定機能病院」や、病床が200床以上ある「地域医療支援病院」および「紹介受診重点医療機関」です。
徴収される金額は病院ごとに異なりますが、初診の場合は7,000円以上(歯科の場合は5,000円以上)、再診の場合は3,000円以上(歯科の場合は1,900円以上)と定められています。また、病床が200床以上ある病院についても、それぞれの病院が設定した金額の特別料金がかかります。
ただし、以下のような場合は特別料金がかかりません。
- ① 救急の患者
- ② 国の公費負担医療制度の受給対象者
- ③ 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る)
- ④ 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者
- ⑤ エイズ拠点病院におけるHIV感染者
出所:厚生労働省「医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。」
※詳細は厚生労働省または病院のウェブサイトで必ずご確認ください。
※上記以外にも、特別料金がかからないケースもあります。
選定療養費には健康保険が適用されず全額自己負担となるため、医療費の負担も大きくなってしまいます。
紹介状を書いてもらうにも費用はかかりますが、上記の選定療養費と違って健康保険が適用されるため、直接大きな病院へ行くよりも負担を抑えられる可能性があります。
紹介状を書いてもらうには、かかりつけ医にまず相談するのが良いでしょう。患者さんが希望した場合、またはかかりつけ医が必要だと判断した場合に、紹介状を書いてもらえます。
健康診断の結果や日常生活の中で感じた自覚症状など、健康面の不安を相談しやすいかかりつけ医を見つけておくことは大切です。
厚生労働省では、地域の医療機関の情報を調べられる「医療情報ネット(ナビイ)」というサイトも用意していますので、活用してみてください。
ジェネリックを選ばないと選定療養費が必要に?
2024年からは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(新薬)の処方を希望した場合にも、選定療養費がかかるようになりました。
ジェネリック医薬品は、特許が切れた新薬と同じ有効成分を使い、それでいて新薬よりも安価であるのが特徴です。
厚生労働省ではジェネリック医薬品の活用を推奨しており、実際に病院や薬局に行った際にジェネリック医薬品を処方されることもあるでしょう。
 ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望した場合にも選定療養費がかかるように
ジェネリック医薬品がある先発医薬品の処方を希望した場合にも選定療養費がかかるように医療上の必要性がある場合やジェネリック医薬品の在庫がない場合以外で、新薬の処方を希望した場合には、新薬とジェネリック医薬品との価格差の4分の1を特別料金として徴収されます。
ジェネリック医薬品に対して漠然と不安な気持ちを持っていて、なんとなく新薬を選んでいた、という人もいるかもしれません。
しかし、不安をそのままにしながら特別料金を徴収されてしまうのは、なんだかもったいない気もしませんか?
もしも不安な気持ちやわからないことがある場合には、まずはお薬を処方してくれる薬剤師や薬局で質問や相談をしてみてくださいね。
参考URL
- 厚生労働省「保険外併用療養費制度について」
- 厚生労働省「医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。」
- 厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」