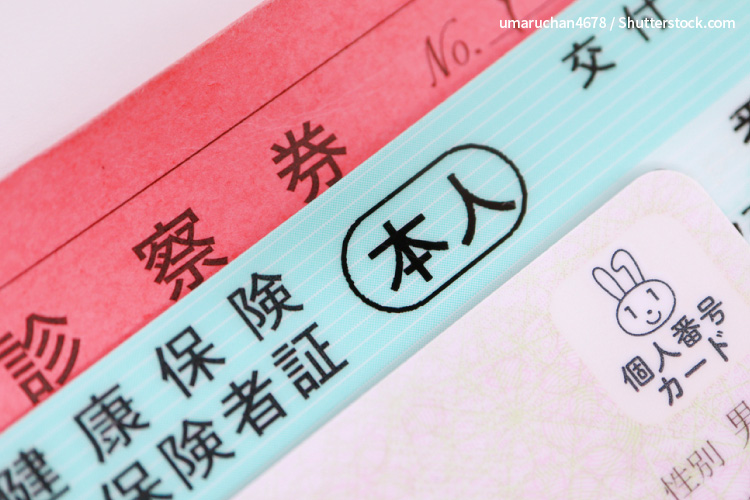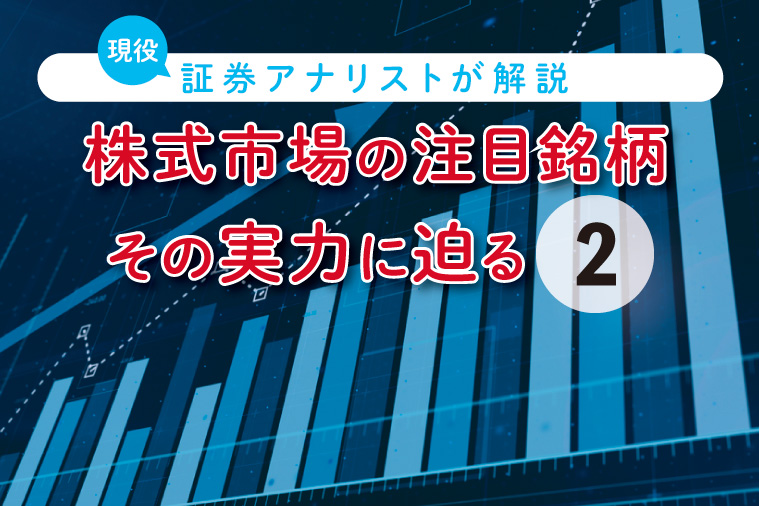2024年12月2日、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用が本格化しています。このほかにも、マイナンバーカードにはさまざまな機能が追加されてきました。具体的にどのようなことができるのか、解説していきます。
- マイナンバーカードの保険証利用で、さまざまな手続きが簡便になる
- 高額療養費制度の利用は、事前手続き不要で、窓口支払いを限度額までに抑えられる
- 2025年3月からは運転免許証利用も予定されている
2024年12月現在、マイナンバーカードでできること
12桁のマイナンバーが記載されたマイナンバーカードには、ICチップが埋め込まれており、様々な機能を持っています。2024年12月時点では、以下のようなことができるようになっています。
マイナポータルを経由しての申請手続き
- コンビニでの証明書交付
- 子育て関連の手続き(妊娠の届け出、保育園入園申し込み、児童手当認定請求手続きなど)
- 引っ越し関連の手続き(転出届の提出、転入届提出のための来庁予定申請(転入届の提出は来庁のみ))
- パスポート申請(更新、新規申請は一部地域のみ)
- 年金関連の手続き(国民年金への切り替え、国民年金保険料の免除・猶予申請など)
- 所得税確定申告時のデータ連携(控除情報、給与所得源泉徴収票情報など)
- 公的給付金受取口座の設定
健康保険証利用
健康保険証利用では高額療養費制度などの手続きが簡便に
特に最近話題となっているのが、マイナンバーカードの健康保険証利用です。マイナンバーカードでの健康保険証利用を開始すると、医療機関・薬局での受付や公的医療制度の手続きなどが、以下のように簡便になります。
①医療保険・薬局での受付が自動化される
病院を受診する際に専用のカードリーダーでマイナンバーカードのICチップ読み取りと、顔写真認証または暗証番号入力をすれば、受付を完了できます。
② 限度額以上の支払いについて手続きが不要になる
病気やケガで月の医療費負担が限度額以上となった場合、高額療養費制度を利用できます(詳しくはこちらの記事でご説明しています)。高額療養費制度を利用する場合、一度は窓口で費用を負担し、その後限度額を超えた分の払い戻しを受けるのが一般的な流れですが、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、事前の手続きなしに、窓口での支払いを限度額までに抑えられます。
③ 加入している健康保険が変わっても継続して利用が可能
就職や転職、引っ越しなどで、加入している健康保険の種類に変更があっても、マイナンバーカードを利用していれば切り替え手続きが不要になります。
④ 処方された薬の情報や特定健診結果を確認できる
特定健診(メタボ健診)や後期高齢者健診を受けた結果や、過去に処方された薬の情報が、政府運営のオンラインサービス「マイナポータル」から確認できるようになります。また、本人の同意があれば医師なども、その情報を確認でき、適切な処方を受けられるようになります。
⑤ 確定申告時に医療費控除の手続きが簡便に
通常は確定申告時に領収書などを基に申告書への入力が必要ですが、マイナポータル経由で医療費などの自動入力が行われます。
健康保険証利用の申し込みは、パソコンや対応スマートフォンで、マイナポータルの専用ページから行えます。パソコンの場合は専用のICカードリーダーが必要になりますので、あらかじめ電気量販店などで購入しておきましょう。セブン銀行のATMからも24時間手続きが可能です。
従来の健康保険証新規発行は終了していますが、利用自体は退職などをしない限り、2025年12月まで利用できます。また、 マイナンバーカードを持っていない場合は経過措置として資格確認書での受診も可能です。ただしいずれの場合も上記のメリットは受けられませんので、ご留意ください。
 マイナンバーカードの保険証利用には、手続きの簡略化など、多くのメリットがある 写真:umaruchan4678 / Shutterstock.com
マイナンバーカードの保険証利用には、手続きの簡略化など、多くのメリットがある 写真:umaruchan4678 / Shutterstock.com2025年3月には運転免許証利用も開始
マイナンバーカードの機能は順次拡充されており、2025年3月24日からは運転免許証との一体化(以下、マイナ免許証)も予定されています。健康保険証とは異なり、運転免許証を継続して保有することも、マイナ免許証と運転免許証の併用もできます。
マイナ免許証の利用で免許の新規取得や更新時の手数料値下げや、講習のオンライン受講などが可能になります。
これ以外にも、今後機能がさらに拡充される見込みですので、マイナンバーカードを持っている方あるいは持とうか検討中の方はぜひチェックしてみてくださいね。
参考URL
- デジタル庁「マイナンバーカードの利用シーン」

- デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」

- マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」

- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

- 警視庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」